中日少子化比较定稿.docx
《中日少子化比较定稿.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《中日少子化比较定稿.docx(18页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
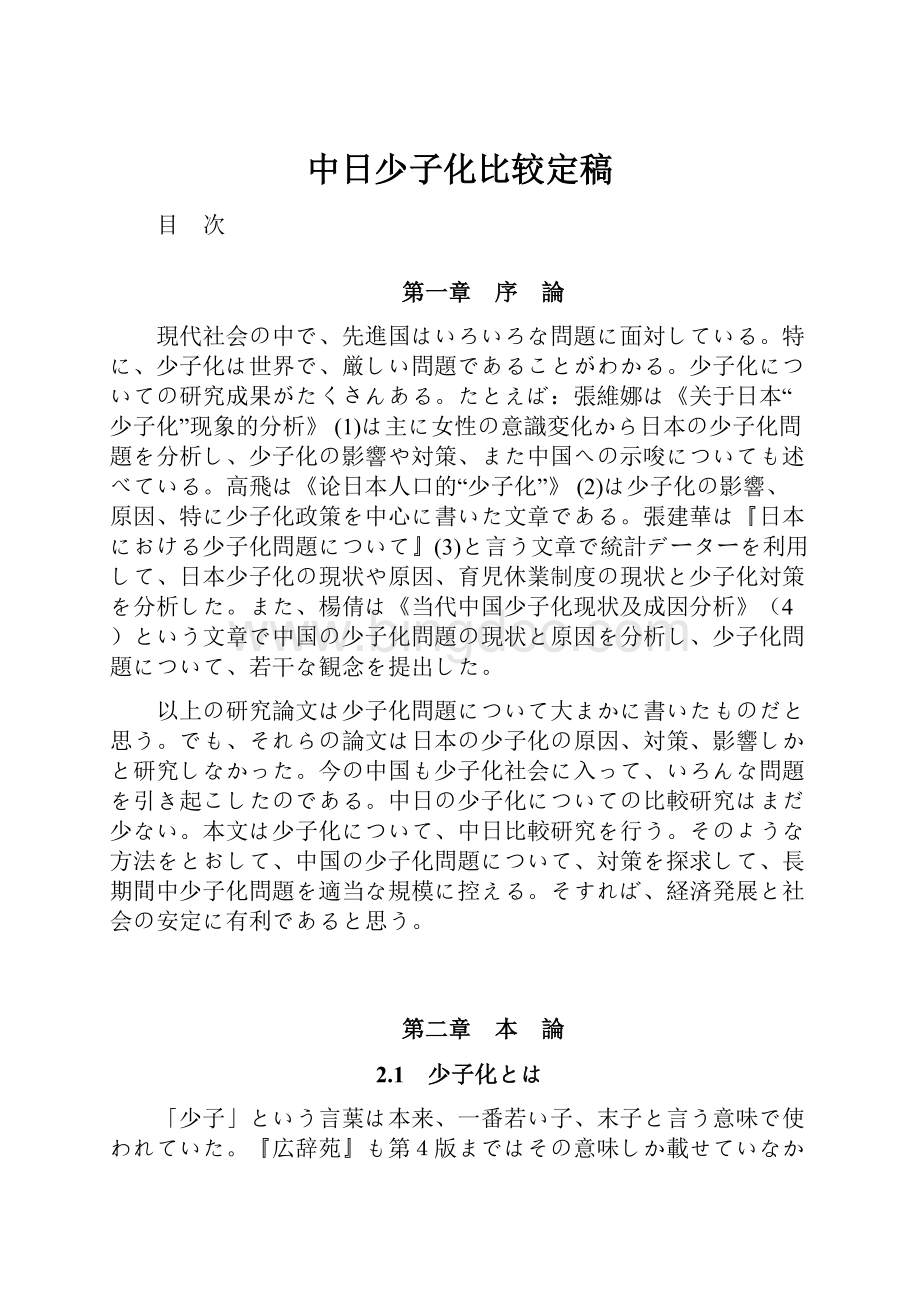
中日少子化比较定稿
目 次
第一章 序 論
現代社会の中で、先進国はいろいろな問題に面対している。
特に、少子化は世界で、厳しい問題であることがわかる。
少子化についての研究成果がたくさんある。
たとえば:
張維娜は《关于日本“少子化”现象的分析》
(1)は主に女性の意識変化から日本の少子化問題を分析し、少子化の影響や対策、また中国への示唆についても述べている。
高飛は《论日本人口的“少子化”》
(2)は少子化の影響、原因、特に少子化政策を中心に書いた文章である。
張建華は『日本における少子化問題について』(3)と言う文章で統計データーを利用して、日本少子化の現状や原因、育児休業制度の現状と少子化対策を分析した。
また、楊倩は《当代中国少子化现状及成因分析》(4)という文章で中国の少子化問題の現状と原因を分析し、少子化問題について、若干な観念を提出した。
以上の研究論文は少子化問題について大まかに書いたものだと思う。
でも、それらの論文は日本の少子化の原因、対策、影響しかと研究しなかった。
今の中国も少子化社会に入って、いろんな問題を引き起こしたのである。
中日の少子化についての比較研究はまだ少ない。
本文は少子化について、中日比較研究を行う。
そのような方法をとおして、中国の少子化問題について、対策を探求して、長期間中少子化問題を適当な規模に控える。
そすれば、経済発展と社会の安定に有利であると思う。
第二章 本 論
2.1 少子化とは
「少子」という言葉は本来、一番若い子、末子と言う意味で使われていた。
『広辞苑』も第4版まではその意味しか載せていなかった。
1992年度の国民生活百書で出生率の低下による子供の数が減少と言う意味で「少子化」という言葉が使われた以後、「若い」ではなく、「数が少ない」と言う意味で使われようになった。
日本国語辞典の解釈で、子供の数が減少する事、あるいは、総人口に占める子供の人口の割合が低下することである。
(5)
いろいろな原因は少子化を起こす。
主なのは現代人の晩育傾向は女性の平均生育数を減少することと、女性は社会活動に参加することと、生活方式が変わた。
結婚、育児は人生の中で先後順序は変わり、結婚と育児は教育環境の要求を高くすることである。
若干な国や地域、結婚と生育は文化に密接な関係がある。
晩育と不育は晩育化傾向と終身未婚率の増加の直接な原因だと考えられている。
2.2 少子化の現状
2.2.1 日本少子化の現状
日本は1997年に子供の数が高齢者人口よりも少なくなり、以降は「少子化社会」になった。
1872年の日本の総人口は3480万人(6)と達した、その後毎年平均1%前後の伸び率で増加し、1967年には1億に昇った。
2003年10月時点では1億2760万人(7)で過去最高の人口となった。
しかし、まもなく総人口が減少する「人口減少社会」を迎えるようになった。
第一次ベビーブーム期は「1947-1949」、第二次は「1971-1974」には約200万人(8)達したが、1975年出生数の減少が続いている。
合計特殊出生率も1970年半ばから約30年間人口置き換え水準を下回っている。
2003年には出生数は112万人(9)、合計特殊出生率は1.29(10)と、いずれも戦後最低の水準となった。
注:
27
しかも、日本厚生労働省の調査報告を通して、いまや日本の晩婚化、少子化、高齢化等の現象は厳しく、日本厚生労働省の機関社会保障人口問題研究所は「出生動向、基本調査」を目標に毎5年行われている。
この研究所は50歳以下の女性に対して、6949個の初婚家庭の調査を通して,平均初婚年齢男性は28.5歳、女性は26.8歳、5年前の調査に比べて、女性晩婚の傾向はさらに明らかである。
結婚時間は5年未満の家庭の中で、子供がほしい数は初めて2人子供以下に減少した。
ほかに一人っ子の家庭は増加した。
日本総務省の最新の調査報告も指摘した。
日本の65歳以上の高齢者は総人口の21%を占め、世界第一である。
15歳未満の人口は総人口の13.6%を占め、世界最低の記録であり、日本の少子化はとても厳重であることがわかる。
2.2.2 中国の少子化の現状
今、中国は発展途上国であればこそ、経済はきわめて不平均である。
東西は不平均で、南北も不平均である。
しかも、少子化は今先進地区にある。
中国では経済は非常に達すなのは上海、北京、広州などである。
だから、その地区で、少子化が明らかである。
代表として、ここでは上海の少子化について紹介する。
上海は中国の発達地区として、少子化は厳重である。
中国では、長い間に戸籍制度を実行しているのは、農村人口を城市人口からためである。
だから、上海の少子化は戸籍制度の影響で、2種類の人口がある。
外来人口と戸籍人口である。
改革開放の前、少子化は明らかではなかったが、1990年代に入ってから、上海の戸籍人口は1993年から持続な自然負増長が現れた。
さらに改革開放の深化を伴って、政府は人口の移転のコントロールをゆるめた。
外来人口の移転規模は迅速に増大している。
しかも、“常住化”趨勢になっている。
したがって、戸籍人口の少子化の発展は常住人口に比べて、程度は厳しい.たとえば、1990年戸籍人口と常住人口の少子化水準10-14歳で、少子人口は総人口を占める比重は18.25%(11)と18.23(12)%。
でも、2000年に入っている、戸籍人口と常住人口の少子化水準は11.98%(13)と11.46(14)%。
こんなデータを見ると、上海の少子化はもう厳重である。
以上述べたように、日本の少子化はだんだん深刻になっている。
中国は少子化の初期である。
なぜそういわれるのか、日本は先進国である。
1947年から、少子化の問題が出た。
60年間にわたって、盛期に達したと思う。
中国は発展途上国であるので、地区の発展区別は大きく、経済水準も大きな違いがある。
こんな原因で経済発達の地区は少子化が現れた。
もうひとつの原因は中国特殊の国情だと思う。
以前から中国は戸籍制度を実行することも少子化に影響した。
だから、次は影響、原因と対策との三つの方面から比較する。
2.3 少子化の影響
2.3.1 日本の少子化の影響
2.3.1.1 人口の減少
2005年から、日本の人口はずっと持続な減少である、2005年、日本の総人口は1億2777万人(15)。
でも、2030年まで、人口は1億15022万人(16)になるかもしれない、さらに、2046年人口は9938万人(17)、2055年まで、人口は8993万人(18)である。
中で14歳以下の人口の減少は明らかである。
2007年、日本の未満14歳の人口は1724万人(19)である。
2009年、人口は1701万人(20)である。
国力社会保障人口問題研究所の推測によると、2039年、未満14歳の人口は1000(21)万人、2055年まで、わずかな752万人(22)になる。
2.3.1.2 教育への影響
少子化のせいで近年、日本の幼稚園の児童は合併と倒産にあった。
文部科学省の統計によると、2000年後中小学校の倒産は増加する。
2002年から2009年まで、倒産の中小学校が3620所(23)ある。
そのうち、小学校は2317所(24)で、中学は660所で、高中は643所である。
同様に大学校の人数も不足である。
2.3.1.3 子供の成長環境の変化
子供の減少は子供と同年の交流の機会も減少している。
この結果子供が自立心がないので、健康に成長することができない。
その上、受験試験の圧力を加え、子供たちはよく精神が緊張し、寂寞と孤独などを感じる。
こんな環境で成長する人々は現代社会の中で成功することができない。
2.3.1.4 人口年齢の結構への改変
高齢化を前進している。
国連の定義によると、もしこの国または地区の65歳以上の人口は「生産年齢」人口の比率の7%を超える。
すなわち、高齢化に入る。
もし14%を超えると高齢社会といわれる。
日本は1970から65歳以上の人口の比例は7%を超えた。
1995年14%を超えた。
2007年21%を超えた、21.5%になった。
超高齢社会に入った。
1997年高齢人口が総人口の15.4%を占めた。
少齢人口は15.3%である。
高齢人口の比例ははじめて少齢人口を超えた。
2010比例は23.1%と13%である。
2.3.1.5 労働人口社会負担への影響
日本社会保障方式は相互に助け合うということである。
すなわち、労働人口の給料の中で年金を引き去る。
年金を享受する老人に送る。
この制度は労働者と年金は絶えずに増加する前に成立したのである。
でも、少子化はさらに厳重になって、年金は減少しつつある。
こんな社会保障制度の負担も必ず重くなる。
日本国民の生活水準にも影響する、最終には経済の可持続発展に影響する。
2.3.1.6 労働人口の供給の減少
少子化のせいで、2010年日本の労働人口は8129万人で、2055年は4595万人に減少する見込みである。
労働人口の減少は労働供給の縮小を引き起こす。
児童数量の減少も需給の縮小も日本経済増長の妨害になる。
2.3.1.7 労働人口の年齢の増加
日本総務省の統計によると、65歳以上の老人の中で、32.2%は依然として働いている。
老人は体力と脳力は衰弱しているによって、従事の仕事は時間が短く強度が低いので、退職人員が絶えず増加することは労働人の上昇を制約する。
その上、人口高齢化で社会が新知識と新観念を吸収速度が落ちる。
技術創新能力も下げる。
国際にとって、総合国力の競争の本質は人材と労働力の競争である。
青年労働人をけなすことは日本の本来の高技術開拓と国際社会のさまざまな競争の邪魔になっている。
2.3.1.8 日本政府の政策の影響
日本の小泉内閣は少子化問題に対して、国民生育率を上げるために、内閣で初めて少子化男女共同参画担当大臣を設立した。
その後、暦任の首相も少子化対策担当大臣を設立している。
少子化問題に向かって、専門研究を設立し、しかも政策を実行する過程に大量の調査仕事をおこなわれている。
2.3.2 中国の少子化の影響
2.3.2.1 経済増長への影響
中国は世界で人口第一大国である。
改革開放が始まって、ずっと「労働密接型」路線を歩き、それから「知識技術密接の路線」に接近する。
経済増長方式は長い間に「粗放型」の方式から「集約型」の方式に転変する。
でも、こんな時期、経済の増長は豊かな労働力資源を頼りにする。
でも、中国は少子化社会に入ってから、労働力供給不足と労働年齢結構をかえるなどの問題がある。
実際、2003年から、中国の南方地区の「民工潮」の状況は「民工荒」に変えた。
2005年まで、「民工荒」の状況は中国の東部沿海からだんだん西部地区に拡大し始めた。
厳しい状況で、中国は自分の豊かな労働力資源に頼り、経済を発展する。
経済増長方式の改変はまだ成功していない。
2.3.2.2 人口高齢化への激化
中国で計画生育政策が行われている。
だから、中国はいま「一人っ子」の国である。
「一人っ子」政策は人口高齢化を激化した。
20年間、老人の人口数量は児童の数量を超えた。
その上、本世紀の中期、労働力は23%に減少する。
そんなとき、33%(25)の中国人、すなわち、4.38億人,60歳以上に達して、アメリカの総人口を超える。
これらはさまざまな高齢社会問題を引き起こす。
たとえば、労働力の不足とか社会結構を打ち付けるとかなどのことである。
最も重要なのは養老問題である。
中国にとって、それは大きな養老危機である。
中国の社会保障制度は完善していない。
医療保険制度の改革はまだ行う必要がある。
こんな状況で少子化社会に入ると、現行の養老保険制度と政府の財政にとって厳しい打撃である。
2.3.2.3 教育への打撃
近年、中国の高考を志願する人数はずっと増長している。
教育部のデータをによると、2002年から2008年まで、全国の高考を志願する人数は527万人から1050万(26)に達した。
でも、『中国青年報』の最新のデータによると、広東、江蘇、重慶などの省を除いて、全国大量の省の人数は減少している。
同時に、中国は絶えずに高等教育の進入学率を下げている。
多くの大学の拡大シテイルを行っているので、少子化は間違いなく教育基礎施設と教育資源を浪費している。
中国の教育制度は日本と同じではなく、学校の経営と建設は国家と政府に頼る。
大部分の学校は公立学校である。
同時に、教師の大部分は編制がある。
こんな体制で、もし「少子化」のせいで、学校が関門されば、教師はどうするのでしょうか。
これはきっと政府の難点になる。
2.3.3 比較
以上述べたように、中国では、子供がほしくないの若者は珍しくない。
経済発達の地域では最も深刻である。
しかも、中国の老人も多くなっている。
つまり、少ない若者は必ず自分より多くの老人を供養する。
それは日本と同じである。
日本では、長時間で少子化問題に面対して、教育、経済、社会保障制度から多い面を打撃している。
しかし、中国はまだ少子化問題の初期なので、少子化についての影響はまだ激しく表れていない。
日本の少子化問題は大変なので、だからこそ、日本の少子化の教訓をおよみ、中国は今必ず慎重に解決しなければならない。
2.4 少子化の原因
以上は中日両国の少子化の影響を考察してみたが、これから、両国少子化の原因を分析してみよう。
2.4.1日本少子化の原因
2.4.1.1 婚姻観と生育観の変化
日本の少子化は男女の晩婚と不婚と子供がほしくない現象に関連がある。
現代は高学歴を持っていて、いい仕事をするの女性は多いので、晩婚の観念が形成した、生育の年齢は1950年の23歳から1998年の26.7歳になった。
それで、子供の数は減少している。
2.4.1.2 女性の意識の変化
生活の質量が変化しているにつれて、日本女性は家庭主婦になることに不満を持ってきた。
彼女たちは社会の中で、自分の人生意義を探したがる。
その上、この目標を目指して努力している。
もうひとつの原因は犬だと思う。
犬は可愛くて、安い。
「子供の出費だって、、幼稚園から大学まで、高い費用がある」。
でも、犬は割りに早く「お手」「お座り」などを覚えられる。
犬は子供より早く成長するのでそんなに面倒くさくない。
もし嫌になったら、どこにでもおいてもいいということ。
若い女性は犬が大好きと思う。
だから、これは女性たちは子供がほしくないのもうひとつの原因である。
2.4.1.3 独身者の増加
調査によると、1970年、日本の独身者の比例は約3.4%で、1995年は約5.1%で、特に、80年代の若者の中、決して結婚しない不婚者は16.8%である。
だからこそ、子供を産むことも減少している。
同時に、子供の養う費用も絶えず増長しているので、家庭の経済負担は重い。
1994年、日本厚生省の統計によると、日本で子供が生まれてから大学を卒業するまでの費用は約200万円が必要である。
家庭にとって、大きな費用である。
これも少子化の原因である。
2.4.1.4 価値観の変化と多様化
経済の発展に伴って、人民の生活は豊富になっている。
女性たちの高学歴を持っていて、仕事する意欲が強くなった。
もし、子供と仕事の中で、矛盾があったら、女性達の大部分はきっと仕事を選ぶようになっる。
現代の日本人は独立で、自由を求めている。
でも、結婚をしたら、自由を失う恐れがある。
2.4.1.5 政策の不完全
少子化に向かって、日本政府はさまざまな政策を実行している。
でも、効果はあまりよくない。
しかも、日本政府は子供を養う補助は不足である。
話によると、1999年日本の支出の社会保障費用は75万億円、その中で、高齢化に対する資金は68%であるが、子供に面する補助は僅か3%で、差額は大きい。
2.4.1.6 離婚率と移民
家庭暴力、仕事などの原因で、離婚の人数は多くなった、特に、近年、「熟年離婚」は流行している。
どうしてかというのは夫は退職後、「粗大ごみ」になる。
中の原因は明らかにされていない。
みんなの生活に影響するとが考えられる。
しかも、近年、いろいろな原因で海外に移民するの人数も増長している。
これも少子化の原因である。
2.4.2 中国の少子化の原因
2.4.2.1 人口の変化
人口の変化は人口の伝統社会の高出生率、高死亡、低増長の状態下、高出生、低死亡、高増長の後から、現代社会の低出生、低死亡、低増長になっている。
全世界で、日本のような先進国はもう人口の変化を完成してた。
中国での人口の変化はまだ初期なのである。
少子化は人口の変化の結果である。
2.4.2.2 経済と科学技術の影響
ヨーロッパ、日本などの先進国は人口の変化を完成したのは経済の発展と科学技術の進歩によるものである。
経済の発展と豊富で生活質量を改善した。
こんな原因で、人口死亡率を下げた。
平均予期寿命を延長している。
それは科学技術の進歩、特に医療技術の進歩と衛生条件の改善にかかっている。
しかも、それも平均予期寿命を延長することに直接な作用がある。
たとえば、1950年代初期、上海の人口死亡率は長期12.80%に維持し、赤ちゃんの死亡率は4%以下であるが、2005年は3.78%ぐらいで日本と同じだる。
同時に、上海人口平均予期寿命として、1951は44.39歳で、2001年は79.66歳で、2005年は80.13歳である。
いわゆる、「長寿の国」日本に追いつく傾向がある。
2.4.2.3 計画生育政策の影響
厳格に計画生育政策を実行するのは中国人口政策の特徴である。
それは中国の生育率を下げる大きな原因だといえる。
計画生育政策の実行は厳重な少子化を引き起こした。
2.4.2.4 「海派文化」と婚育観念の変化
西洋文化の影響で、ディンクス家庭とか同性愛とか独身者とか人数が増加している。
社会競争を激化した。
現在社会では婚育観念が変わった。
特に上海地区の人口は厳しい。
中国で「房奴、子供奴、カード奴」などの名詞が現れた。
現代の若者には責任感が欠け、自分も親のすねをかじという族がある。
だから、彼らは結婚しなく、子供を生むのもしない。
彼らは自分が子供のように、親の配慮が必要だと思っている。
これも少子化の原因である。
2.4.3 比較
以上述べたように、もっとも最大の認識は中国と日本の少子化の大きな原因は同じではない。
日本の少子化のもっとも大きな原因は経済の発展で、また、さまざまな問題を引き起こした。
こんな問題を解決しない限り、人々の思想意識が変わっていけない。
だから、少子化問題は深刻になった。
中国の少子化の原因は中国が計画生育政策を実行していることにある。
この政策は人口量を制御したが、現在、これは少子化の原因である。
でも、中国の総人口多いので、人口を制御しがたい。
2.5 少子化に対する対策
中日両国とも少子化の問題が存在しているが、上述において、少子化の現状、影響を考察した上で、原因を探求したが、この問題に対し、どんな対策を打てるのか、これから述べてみよう。
2.5.1 日本の少子化対策
日本において、政府が、出生率の低下と子供の数が減少傾向のことを「問題」として認識し、子育て支援の対策に取り組みはじめたのは、「1.57ショック」がそのきっかけとなった1990年以降のことである。
「1.57ショック」とは、1990年になって、前年の合計特殊出生率が1.57%と、「ひのえうま」という特殊要因による過去最低であった1966年の合計特殊出生率1.58%を下回ったことが判明したときの衝撃をさしている。
「1.57ショック」をきっかけに、厚生省が中心となった。
仕事と子育ての両立支援など子供をうみそだてやすい環境づくりに向けての対策の検討がおこなわれはじめた。
2.5.1.1 エンゼルプランと新エンゼルプラン
最初の具体的な計画が、1994年12月、文部、厚生、労働、建設の四大臣合意により策定された『今後の子育て支援のための施策の基本的方向について』「エンゼルプラン」であった。
エンゼルプラン、子育てを夫婦や家庭だけの問題ととらえるのだけでなく、国や地方自治体をはじめ、企業、職場や地域社会も含めた社会全体で子育てを支援していくことを狙いとし、政府部内において、今後10年間に取り組むべき基本で方向と重点施策を定めた計画であった。
エンゼルプランを実施するため、保育所の量的拡大や低年齢児(0-2歳児)保育や延長保育などの多様な保育サービスの充実、地域子育て支援センター整備などを図るための『緊急保育対策など5か年事業』が策定され、1999年度を目標年次として、整備がすすめられることとなった。
その後、1999年12月、少子化対策推進関係閣僚会議において、『少子化対策推進基本方針』が決定され、同年同月、この方針に基づく重点施策の具体的実施計画として、「重点的に推進すべき少子化対策の具体的実施計画について」(新エンゼルプラン。
大蔵、文部、厚生、労働、建設、自治の6大臣合意)が策定された。
新エンゼルプランは、従来のエンゼルプランと緊急保育対策等5か年事業をみなおしたもので、2000年度を初年度として2004年度までの計画であった。
最終年度に達成すべき目標値の項目には、これまでの保育サービス関係だけでなく、雇用、母子保健、相談、教育の事業も加えた幅広い内容となった。
2.5.1.2 次世代育成支援対策推進法
2003年7月、『次世代育成支援対策推進法』が制定された。
これは、地方公共団体および事業主が、次世代育成支援のための取り組みを促進するために、それぞれ行動計画を策定し、実施していくことを狙いとしたものであった。
法律の概要は次のとおりである。
まず、国は、地方公共団体および事業主が行動計画を策定するにあったて拠るべき方針を策定することである。
次に、市町村および都道府県は、国の行動計画策定方針に即して、地域における子育て支援、親子の健康の確保、教育環境の整備、子育て家庭に適した居住環境の確保、仕事と家庭の両立などについて、目標および目標達成のために講じる措置の内容を記載した行動計画を策定することである。
それから、事業主は、国の行動計画策定方針に即して、次世代育成支援対策の実施による使用とする目標および目標達成のための対策等を定めた一般事業行動計画を策定し、行動計画策定方針に即して、目標、目標達成のために講じる措置の内容などを記載した行動計画を策定し、公表することである。
また、事業主からの申請に基づく行動計画を定めた目標を達成したことなどの基準に適合する事業主を認定することである。
一般事業主の行動計画を策定した旨の届出については、301人以上の労働者を雇用する事業主は義務付け、300人以下は努力義務とされた。
地方公共団体および事業主の行動計画策定に関する規定は、2005年4月から施行された。
2.5.1.3 少子化社会対策基本法と少子化社会対策大綱
2003年7月、議員立法により、[少子化社会対策基本法]が制定され、同年9月から施行された。
この法律は、日本における急速な少子化の進展が、21世紀の国民生活に深刻かつ多大な影響をもたらすものであり、少子化の進展に歯と目をかけることが求められているとの認識に立ち、少子化社会において講ぜられる施策の基本理念を明らかにするとともに、少子化に的確に対処するための施策の方針として、総合的かつ長期的な少子化に対処するための施策の大綱策定を政府に義務付け手織り、それを受けて、2004年6月、[少子化社会対策大綱]が少子化社会対策会議を経て、閣僚決定された。
この大綱のキーワードは、「少子化の流れを変える」である。
すなわち。
少子化の急速な進行は、社会、経済の持続の可能性を揺るガス危険的なものと真摯に受け止め、子供が健康に育つ社会である。
子供を生み、育てることに喜びを感じることのできる社会への転換を喫緊の課題とし、少子化の流れを変えるための施策に集中的に取り組む