语汇史.docx
《语汇史.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《语汇史.docx(15页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
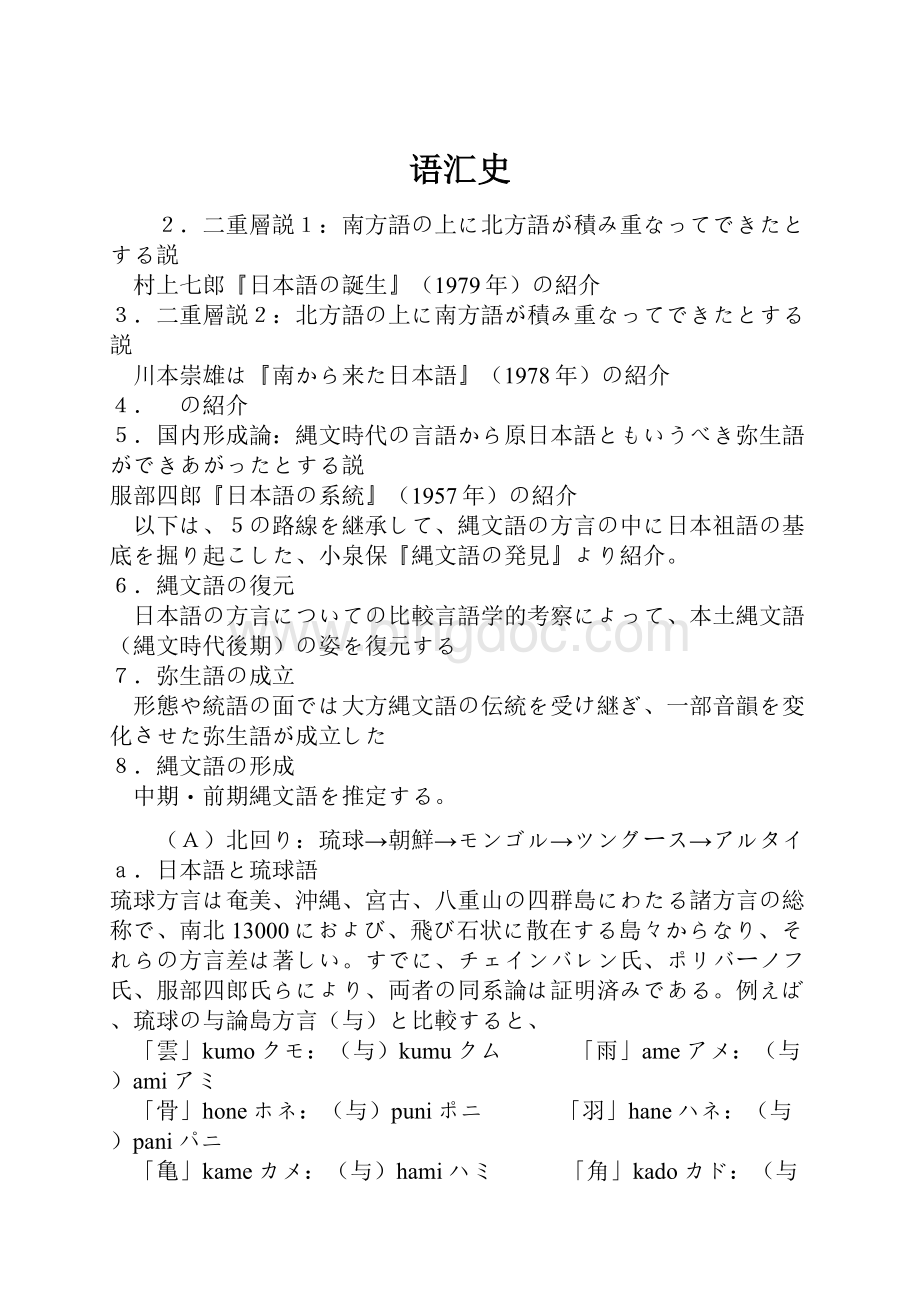
语汇史
2.二重層説1:
南方語の上に北方語が積み重なってできたとする説
村上七郎『日本語の誕生』(1979年)の紹介
3.二重層説2:
北方語の上に南方語が積み重なってできたとする説
川本崇雄は『南から来た日本語』(1978年)の紹介
4. の紹介
5.国内形成論:
縄文時代の言語から原日本語ともいうべき弥生語ができあがったとする説
服部四郎『日本語の系統』(1957年)の紹介
以下は、5の路線を継承して、縄文語の方言の中に日本祖語の基底を掘り起こした、小泉保『縄文語の発見』より紹介。
6.縄文語の復元
日本語の方言についての比較言語学的考察によって、本土縄文語(縄文時代後期)の姿を復元する
7.弥生語の成立
形態や統語の面では大方縄文語の伝統を受け継ぎ、一部音韻を変化させた弥生語が成立した
8.縄文語の形成
中期・前期縄文語を推定する。
(A)北回り:
琉球→朝鮮→モンゴル→ツングース→アルタイ
a.日本語と琉球語
琉球方言は奄美、沖縄、宮古、八重山の四群島にわたる諸方言の総称で、南北13000におよび、飛び石状に散在する島々からなり、それらの方言差は著しい。
すでに、チェインバレン氏、ポリバーノフ氏、服部四郎氏らにより、両者の同系論は証明済みである。
例えば、琉球の与論島方言(与)と比較すると、
「雲」kumoクモ:
(与)kumuクム 「雨」ameアメ:
(与)amiアミ
「骨」honeホネ:
(与)puniポニ 「羽」haneハネ:
(与)paniパニ
「亀」kameカメ:
(与)hamiハミ 「角」kadoカド:
(与)haduカドウ
母音(オ:
ウ)、(エ:
イ)が対応し、子音[h:
p]、[ka:
ha]が対応し、語中の子音についても[-m-][-n-][-d-]が共有されている。
規則的音声対応は、このように語の頭位、中位、末位のいずれにおいても音声の一致もしくは対比が成立しなければならない。
頭位の音のみを比べる[頭合わせ]は単なる類似の域をでない。
とにかく、琉球語こそ現代日本語との間に規則的音声対応が見出されるただ一の同系言語である。
b.日本語と朝鮮語
明治以来日本語と朝鮮語の同系を主張する学究の数は多いが、いずれも比較言語的な根拠をもたない。
c.日本語とモンゴル語
日本語の一音がモンゴル語では多様に変わっており、複合対応に関して何も論拠が示されていない。
d.日本語とツングース語
両者には音韻法則を立てるための確実で豊富な対応語例が見つからない。
e.日本語とアルタイ語
モンゴル語は中央アジアのチュルク諸語および東アジアのツングース諸語とともにアルタイ語族を形成するという見方がある。
これが言語学史上有名な「アルタイ語説」である。
藤岡勝二氏は明治41年(1903年)「日本語の位置」と題した講演で、日本語とウラル・アルタイ諸語と通有する類型的特徴を14項目にまとめている。
ウラル語はウラル山脈の西側で話されているフィンランド語とハンガリー語に代表される語族である。
以下、主としてトルコ語(ト)の例を用い、ウラル・アルタイ語と日本語が共有する特徴を略述すると、
[A]音声的特徴
(1)語頭に重子音がこない(子音が連続しない)
(2)語頭にr音がこない (「ロシア」は以前「オロシャ」と呼ばれたいた)
(3)母音調和と呼ばれる語を構成する母音についての制約がある
[B]形態的特徴
(4)文法上の性がない (ドイツ語には女性名詞、男性名詞のような文法性の別がある)
(5)動詞変化では、語幹に接尾要素が付加される ((ト)oku-t-ul-du「ヨマ・サセ・ラレ・タ」)
(6)動詞語尾の種類が多い
(7)代名詞の変化では助詞が付着する ((ト)bun-dan「コレ・カラ」)
[C]統語的特徴
(8)冠詞を用いない (英語には定冠詞theがある)
(9)後置詞を用いる ((ト)kalemile「ペン・デ」)
(10)所有はhave「~をもつ」ではなく、「~がある」と表現される (彼ノ(モノ)・本ガ・アル)
(11)形容詞の比較は奪格「~ヨリ」の形を用いる
(12)疑問文では文末に疑問の助詞がくる ((ト)okudumu「読ンダ・カ」)
(13)接続詞を用いることが少ない
(14)修飾語が被修飾語の前にくる ((ト)guzelkiz「美シイ・娘」)
目的語は動詞の前にくる ((ト)kitapokudu「本ヲ・読ンダ」)
こうした論拠は、新村出氏「国語系統の問題」(1911)にも受け継がれ、「日本語はウラル・アルタイ語に縁を引くが、その関係は甚だ疎遠である」との結論を出している。
また金田一京助氏は『国語史系統編』(1938)の中で、日本語をウラル・アルタイ語の一員として位置づけ、「文法がほぼ一致する上に、音韻組織にも重要な共通点があるとすれば、この上は、語彙の確実な一致さへ見出されるならば、国語はアルタイ語族に属することが実証されるわけである」という結論を出している。
ところが肝心な語彙の確実な一致が見出されないのである。
その上、現在ウラル語族とアルタイ語族を一まとめにする見方は保留されているし、アルタイ語族自体の成立も疑問視されている状況にある。
(B)南回り:
南島諸島→タミル→チベット・ビルマ
a.日本語と南島語(オーストロネシア語)
太平洋とインド洋にかけて散在する島々で話されている言語は「オーストロネシア諸語」と総称されている。
こうした大洋州(オセアニア)に広がる諸言語――インドネシア系のマライ語、メラネシア系のフィジー語、ポリネシア系のサモア語、ミクロネシア系のトラック語――の間には音声の対応が認められ、同系であることは間違いない。
オランダの南島語学者ラベントン氏や松本信宏氏は、次のように日本語を南島語と結び付けている。
(日)「木」ki:
(マライ語)kaju
(日)「魚」uwo:
(ジャワ語)iwak
(日)「顔」kapo:
(マライ語の方言)kapo
(日)「口」kuti:
(サモア語)gutu、(マオリ語)nutu(ともに「唇」の意)
このように、南島諸島の言語の中から似た語形を適宜ひろいあげている。
しかし、比較方法は一つの言語と日本語との間にできるかぎり多数の類似語彙をみつけて、音声対応を検討するのでなければ効力をもたない。
気まぐれな対比は系統についての証明力を欠いていることになる。
b.日本語とタミル語
インド亜大陸の南端部を占有しているドラビダ族、そのドラビダ語の中でもタミル語と日本語との類似が取り沙汰されるようになった。
藤原明氏『日本語はどこから来たか』(1981)、大野晋氏『日本語とタミル語』(1981)など。
しかし例語における複合対応はその原因が究明されなければ、単なる類似の線を越えることができない。
またタミル語は、ドラビダ諸語の基本的特徴である4種類のそり舌音t、n、l、r音をもっているが、日本語で消滅したわけも知りたいものである。
さらに文法的相違も問題となる。
タミル語の名詞には男性、女性、中性という三つの文法性があって、これが助詞の活用にも作用している。
こうした文法性が日本語では消え去って痕跡すらないのはなぜであろうか。
またタミル語の名詞には単数と複数があり、ともに格変化を行なう。
こうした点について納得のいく証明がないと、日本語とタミル語の同系性の承認を得ることは難しいであろう。
c.日本語とチベット・ビルマ語
(省略)
以上、言語の血縁関係を認定する「規則的音声対応」という判定法により、琉球語は間違いなく日本語の分家であることが証明できた。
しかし、その他の言語については、類似していると思われる語彙や文法特徴をいかほど数えあげてその親族関係を主張し合っても、規則的音声対応が取り出せないかぎり水掛け論に終始することになるであろう。
「二重層説」
村山七郎氏の『日本語の誕生』(1979年)を紹介します。
村山氏は元来、アルタイ比較言語学の立場から日本語系統問題を考究していました。
しかし、日本語にはアルタイ起源では説明がつかない語彙があまりに多いという見解に達し、南島語と日本語の比較に注目するようになります。
その結果、いわゆる基礎語彙の約35%、文法要素の一部が南島語起源であり、このような深い浸透は借用と言えるレベルを超えたもので、日本語はアルタイ系言語と南島語の重層して形成された主張します。
(※基礎語彙とは、どんな言語でも共通して不可欠と思われる語彙で、「手・足・目・口・人・もの・言う・食う・寝る・良い・悪い・・・」などがそれに当たります。
)
◆従前の日本語系統論は、北方由来が主流19C以来の日本語系討論は、アルタイ諸語などの北方に由来するという学説が主流でした。
単層説でも取上げられていますが、代表的な根拠をまとめると以下のようになります。
①動詞や形容詞などの用言の活用システムや、語順、代名詞などの主要な文法要素はアルタイ諸語と共通している。
②古代の日本語(大和言葉)において、語頭にr音(流音)が立たないことも共通している。
③基礎語彙の中に、北方系と同じ一種の母音調和がみられる。
※例えば、耳(みみ)、頭(あたま)、頬(ほほ)、身体(からだ)、肘(ひじ)、乳(ちち)、尻(しり)など、同じ母音の連続が顕著に見られ、原始的な母音調和の痕跡をとどめている。
◆村山氏がまとめた南方由来の根拠
前述したように、村山氏自身は北方アルタイ諸語の言語学者でしたが、南方にも由来すると考えた根拠を、以下にまとめます。
①古代日本語における、基礎語彙を含む相当数の語彙(総計して約240語の語彙が比較されている)がオーストロネシア起源である。
②助詞「の」や連濁現象が、オーストロネシア諸語に広く見られるリンカー(繋辞)na/ngを起源とする。
③接頭辞(た走る、ま白、か細し、など)もオーストロネシア起源と推定される。
④オーストロネシア語族の前鼻音化と呼ばれる特異な形態音韻論的現象の痕跡が、古代日本語に残存すると見られる。
⇒∴オーストロネシア語の影響は、語彙だけでなく、統語・形態論的な要素にも及んでいると主張します。
★南方を基層とする根拠は何か?
⇒日本語は北方・南方いずれも影響を受けているということが、村山氏の主張ですが、南方を基層と考える根拠については、文化人類学者の金関丈夫氏の言説に依っています。
金関説では、縄文中期以降にメラネシアやインドネシアなどの南方文化(歯牙変工・文身・崖葬・など)が、沖縄を経由して西日本~中部地方まで及んでいるとされ、この点を南方基層の根拠にしています。
日本語系統論では、現在でも文法が北方由来で、語彙が南方由来とする説が主流のように思われます。
しかし、歴史学・人類学においても、南方・北方のどちらを基層とするかについては未解明な部分が多いため、人類学の一論説に依拠して日本語の基層を南方に置いている点には疑問符が付きます。
村山氏による南方語の上に北方語が積み重なってできたとする、今回は北方語の上に南方語が積み重なってできたとする 「二重層説」を、川本崇雄氏の『南から来た日本語』(1978年)より紹介します。
村山氏は南島語が土着言語で、それがアルタイ化して日本語が成立したと考えておられたようですが、川本氏は南島語は基礎ではなく、後から来てむしろ上層となり、塗り重ねてしまったのだと考えておられるようです。
その理由としては、一般に文法はなかなか変わりにくいが、単語は容易に入れ替えが行なわれること、そして日本語には確実にアルタイ系と見られる単語は少なく、南島系の単語が多いことによるものでした。
しかしこれまで、南島語基礎説を否定できるような明快な理論的な裏づけがないままに時が過ぎてきました。
では、川本氏による南島語基礎説を否定できる明快な理論的な裏づけ(北方語の上に南方語が積み重なってできたとする説)とは何か。
★インドの二重層言語事例
川本氏は、クリシュナムティが書いた『ドラビダ語比較言語学』の中に面白い一節を発見します。
インドは多種多様な言語の存在で有名ですが、現在はおおよそインドヨーロッパ系の言語とドラビダ系の言語の地域に二分されます。
ところがインドヨーロッパ系地域に属するヒンディー語などはインドヨーロッパ語の言葉であるにも関わらず、ドラビダ語独特のrが存在し、語順も動詞の前に目的語が立つドラビダ式になっています。
こうした不思議な現実がどんな経過をたどって成立したかを、クリシュナムは歴史的事実を踏まえて理論付けています。
インドはかつてドラビダ族の国であったが、そこへインドヨーロッパ系のアーリア族が侵入し、支配階級となった。
二つの異質な言語が接触した結果、圧倒的多数のドラビダ族が少数のアーリア族の言語を修得する際に、ドラビダ的な特徴を捨て切ることが出来なかった。
また少数の支配階級も自分達の正しい発音や文法を多数の民衆に徹底させる事は不可能であった。
その結果、支配階級のアーリア語自体も、世代が代わり数百年が経過するうちに、民衆(引用者注:
ドラビダ人)の使うアーリア語に近いものになっていった。
現代のヒンディー語が、インドヨーロッパ系でありながら、ドラビダ語の音声的・文法的特性を具えているのはこのためである。
つまりこれを一般的に言えば、現在インドヨーロッパ系地域に属するヒンディー語とは、多数者の話す土着の言語A(ドラビダ語)の中に、文化的に優れた少数者の話す外来の言語B(アーリア語)が入っていったとき、発音・文法はAを採用する(つまりAに同化する)が、基礎語彙はBのものを保持した言語B’で構成された言語であるといえます。
★南島語は後から来た古代日本語は基礎語彙はもちろん、圧倒的な単語が南島系ですが、文法・音韻的特徴は、南島語的なものとアルタイ語的なものとが併存しています。
従って、上記の理論に従えば、日本語の語彙はヒンディー語のように外来系のB’であることは明白ということになります。
日本列島には縄文時代の末期、アルタイ語的な言葉Aが話されていました。
そこへ秀でた稲作文化を担った南島語族が言葉Bをもたらしました。
土着の人々は新来の高度の文化を吸収するため、外来の言語Bを競って学びました。
外来の人も土着の人も二重言語を強いられました。
自分達の部落に帰れば純粋のBまたはAを用いますが、一たん外へ出ると単語はBのものですが、Aのくせのまじった混合言語B’という共通語を使用しなければなりませんでした。
月日が流れ時代が移るにつれ、外来の人々の家庭では、老人がいくら純粋のBを使用する努力をしても、子や孫は外の同年輩の多くの人々の使用する共通語B’を好むようになります。
かくして百年二百年たつうちには、外来の人たちの家にも、B’しか知らない人達が育つようになるのです。
外の世界では古くさい言語AまたはA’と、しゃれた文化語B’が長い間併存を続けます。
しかし大勢には抵抗できず、やがてAもA’も亡びてしまったのです。
★共認内容は文法ではなく語彙の中にある
上記のインドの学者の理論に従えば、系統的にはA’はAに、B’はBに属します。
そしてその決め手は、昔の言語学者が重視した文法ではなく、むしろ基礎語彙だと川本氏は考えています。
つまり、その共認内容は文法ではなく語彙(or基本語彙)に規定されると考えておられるようです。
そのわけは“ダッシュ”付きのない祖先から受け継いでいるのは基礎語彙であり、極論すると基礎語彙しかないからです。
すなわち、稲作を持ち込んだ南島語族(弥生人)の言語が日本語の起源と捉えていることになります。
以上、川本崇雄氏の北方基層に南島語を塗り重ねて出来た言語を日本語の起源とする重層説をまとめてみました。
川本説はむしろ基本語彙を主軸とした単層説と言ってもいいのかもしれません。
しかし、日本語の起源は、弥生人の言語と考えていいのだろうか縄文人の共認内容は、弥生人の共認内容に塗り替えられてしまったと考えていいのだろうか疑問が残ります。
さて、本題に入る前に安本氏らが重層説に至るためには、それまでの言語学とは異なったアプローチが必要でした。
その経緯をまず氏の著書「日本語の誕生」からご紹介します。
比較言語学の音韻対応の法則
どのような二つの言語をとってもその意味と音が似ている言葉は見つけ出すことが出来る。
例えば、日本語の「そう」と英語の「so」、日本語の「なまえ(名前)」とドイツ語の『ナーメ(name)」、日本語の否定の「ぬ」とフランス語の否定の「ヌ(nu)」などである。
これらが偶然の一致なのか、そうでないかを見分ける方法はあるのであろうか?
これらがこじつけか、そうでないかを弁別する方法はないだろうか?
その偶然性を排除するのが、これまでは比較言語学における音韻対応の法則であった。
従来の比較言語学「音韻対応の法則」とその限界
<音韻対応の法則>の有効範囲
①一つの祖語から二つの言語が分かれる場合、分裂がはじまってから約2500年以内の場合は、一語一語の特殊性があっても、対極的にはほぼ確実に音韻対応の法則が見出すことが出来る。
(これは洋の東西・言語の種類を問わない。
)②二つの言語が分かれてから2500年~5000年になる場合、音韻対応の法則を見出す事が困難になる場合が生じる。
③二つの言語が分かれてから5000年以上たつ場合は、音韻対応の法則を見出す事はほぼ困難になる。
(現在のところ祖語から分かれて5000年以上たっていることが明らかな言語において音韻対応の法則が厳密に確かめられている例はない)
日本語の場合、地理的には一番近い朝鮮の言語でさえ分裂してから5000年を超える可能性が高い。
(東大名誉教授の言語学者服部四郎氏は言語年代学の方法により、もし日本語が朝鮮語から別れたとしても、分裂の時期は7000年以上前になると述べられている)したがって、日本語の起源を探る場合、音韻対応の法則を見出すという方法では、手が届かなくなる。
また、比較言語学において音韻対応の法則が確立していない場合、二つの言語は「同系」であるとはみなされない。
琉球語を除き、世界中の言語の中で日本語と音韻法則が確立した言語は存在しない⇒どうする?
このような比較言語学の限界から、ついに安本氏は数理言語学・語彙統計学(確率論)の可能性に収束し、日本語多重層説へとたどり着く事になります。
語彙(ごい)統計学とは言語年代学ともいわれアメリカの言語学者モリス・スワデシュが確立した学問で、基礎語彙という概念を用いて、二つの言語の一致の度合いが、偶然に起こる確立かどうかを調べ、言語の系統関係を明らかにしようとするものです。
文化的な語彙が他言語から借用される可能性が高いのに対し、この※基礎語彙はそれぞれの言語独自の発展を見せ、借用関係については強い抵抗力・抗体性を持つといわれています。
この基礎的な語彙=基礎語彙とはどんな言語にも見られるもので、例えば、「ある・ない、全部、大きい・・」等の語彙を100語もしくは200語に限定してリスト化し比較を行います。
このリストは比較する全言語について基本的に同一語彙のリストです。
※「基礎語彙」=「手」「目」「耳」などの身体語や、「山」「川」「月」「日」「雲」などの自然や天体に関する語、「鳥」「犬」「木」「葉」「根」などの動植物に関する語、その他をさす。
安本氏・本多氏の唱える多重層説
以下が多大な困難を乗り越え、多くの協力者の力を得て、なんとヨーロッパの諸言語をのぞく四十八言語もの「基礎語彙表」を作成し、語彙統計学によって安本氏らが導き出した結論です。
<前提>統計学上、日本語・朝鮮語・アイヌ語の三つは、語彙において相互に確率的に偶然では起こりえない一致を示している。
また、この3つの言語には「主語→目的語→動詞」の語順などに見られる独特の文法的特長が見られる。
→現代の日本語は、日本語、朝鮮語、アイヌ語の三つの共通する言語から派生し重層している可能性が高い。
●日本語の起源第1層この3つの言語と共通する言語の存在を「古極東アジア語」として想定する。
この共通する古極東アジア語は、1万年から2万年前に日本海を中心とした朝鮮・中国大陸を含む広範囲で使用された言語であったと考えられる。
→この古極東アジア語は統一性をもっていたと考えられる。
その後、気候変動によって日本列島が大陸から分離され各々、古日本語・古朝鮮語・古アイヌ語は方言化し、異なる言語となっていった。
●日本語の起源第2層この古日本語を祖として、初めに台湾のアタヤル語と結びつく語彙が日本に流入したと考えられる。
(アタヤル語等のインドネシア系の集団が、南九州から四国地方に居住)その後、6~7000年前の縄文期にカンボジア語と結びつく、モン・クメール語系の語彙が日本列島に流入したとみられる。
しかし、これらインドネシア語・カンボジア語系の言語は比較的早期に日本列島に流入しているものの、居住域に限定された地域性の強いものであり、当時は列島で統一的に使用された語彙ではないと考えられる。
●日本語の起源第3層更に弥生時代はじめ頃にビルマ系ボド語群(南方語)と結びつく語彙が、稲作文化と共に中国の江南地方からもたらされたと考えられる。
身体語や植物語等、かなり多くの語彙が明快に現在の日本語と結びついている。
第三の波はおそらく、その人口はかならずしも多くなかったであろうが、政治的な力はもっていたであろう。
そして、はじめは北九州に上陸し既に北九州に存在していた(朝鮮祖語との関連を保っていた)古極東アジア語の系統を引く言語と結びつき、日本語祖語を形成したと思われる。
第三の波であるビルマ系江南語は、基本的な語順は古極東アジア語と共通していた。
この勢力は南九州・本州へと勢力をのばすにしたがい、庶民の間にかなり広く広がっていたインドネシア系の言語的要素を飲み込んでいったのであろう。
●日本語の起源第4層 この日本語祖語がその後、中国語の影響を大きく受けて現在の日本語が形成されていったのであろう。
日本語の起源において成り立つのは、その特殊な地域特性から西洋型の「系統論」ではなく、いかにして日本語が成立したかの「成立論」であると安本氏らは言っています。
それは、すなわち、日本語の成立にあたって、日本という器に流れ込んだ言語としてはどのようなものが考えられるか?
それはどのような形で寄与したのかが重要なのだということです。
以上が安本氏らの唱える日本語の成り立ち「多重層説」でした。
安本氏の概念モデルを比較すると、西洋が分化する言語であるのに対し、日本語は日本を器として塗り重なって進化する言語であると言えそうですね。
畳字連歌では漢語の熟語を詠みこんでいく。
「真実の花とは見えず松の雪」に、「明春さこそつぼむ冬梅」というように、真実・明春といったふだんは和歌にも連歌にもつかわない漢語を入れる。
だからふだんから漢詩文と和歌文の両方をマスターしている必要がある。
五・七・五・七・七の和歌形式を、ふたりが応答してよむ詩歌の一種。
また、そういう詩歌を作ること。
ふつう、五・七・五の上の句と、七・七の下の句を別人がよむ形で行なわれる。
短連歌(一句連歌)と長連歌(鎖連歌)に分けられる。
発生期の平安時代には、和歌の上の句と下の句をふたりが唱和する短連歌がもっぱら行なわれていた。
院政期(一二世紀半ば)ごろから、多人数または単独で、上の句と下の句を交互につらねてゆく長連歌に発達し、中世を経て、近世初期まで流行した。
長連歌は、句数によって、歌仙(三十六)・世吉(よよし=四十四)・五十韻・百韻・千句・万句などの形式がある。
第一句を発句(ほっく)、第二句を脇(わき)、第三句を第三と呼び、最終の