日语演讲模版日文版.docx
《日语演讲模版日文版.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《日语演讲模版日文版.docx(18页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
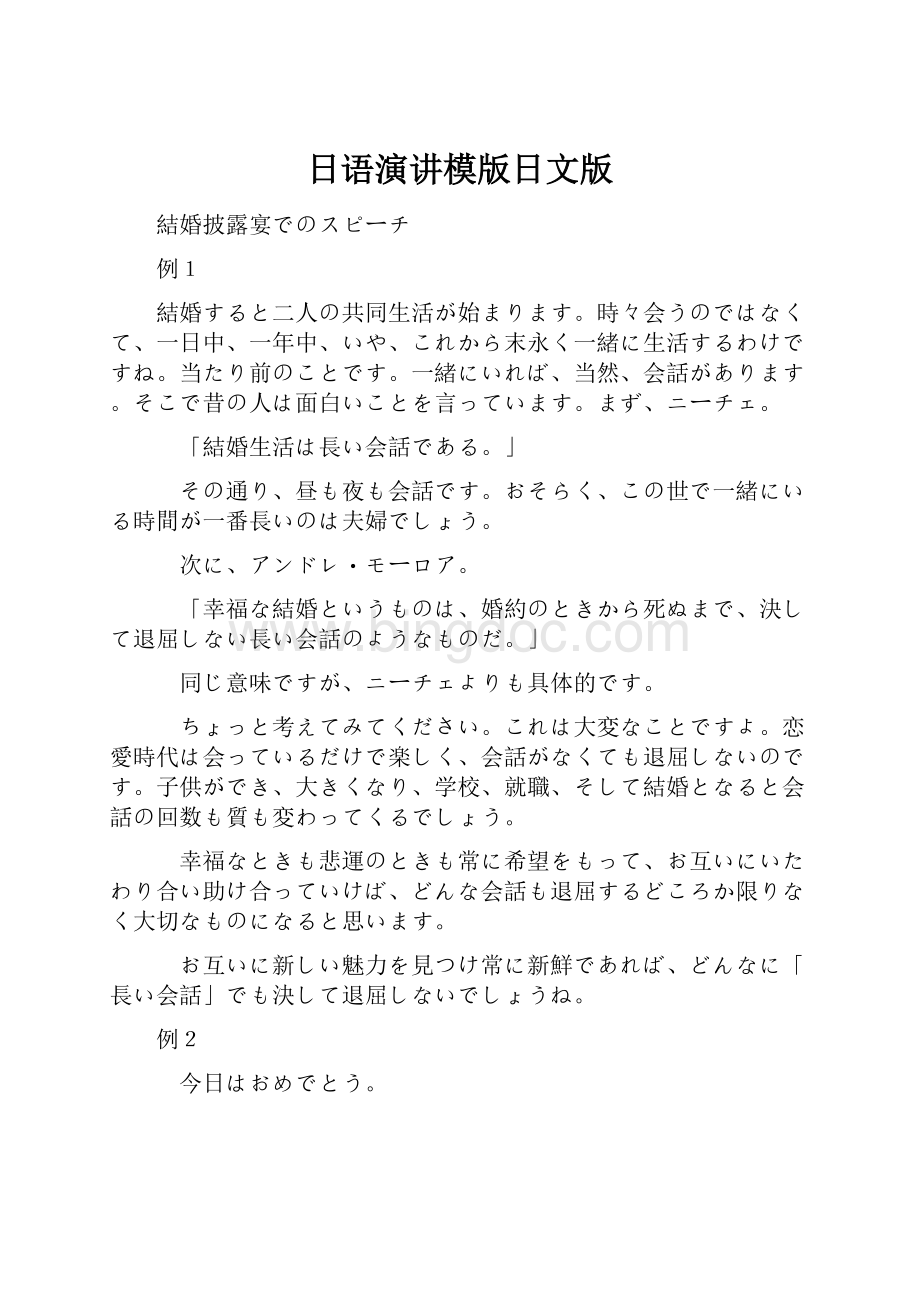
日语演讲模版日文版
結婚披露宴でのスピーチ
例1
結婚すると二人の共同生活が始まります。
時々会うのではなくて、一日中、一年中、いや、これから末永く一緒に生活するわけですね。
当たり前のことです。
一緒にいれば、当然、会話があります。
そこで昔の人は面白いことを言っています。
まず、ニーチェ。
「結婚生活は長い会話である。
」
その通り、昼も夜も会話です。
おそらく、この世で一緒にいる時間が一番長いのは夫婦でしょう。
次に、アンドレ・モーロア。
「幸福な結婚というものは、婚約のときから死ぬまで、決して退屈しない長い会話のようなものだ。
」
同じ意味ですが、ニーチェよりも具体的です。
ちょっと考えてみてください。
これは大変なことですよ。
恋愛時代は会っているだけで楽しく、会話がなくても退屈しないのです。
子供ができ、大きくなり、学校、就職、そして結婚となると会話の回数も質も変わってくるでしょう。
幸福なときも悲運のときも常に希望をもって、お互いにいたわり合い助け合っていけば、どんな会話も退屈するどころか限りなく大切なものになると思います。
お互いに新しい魅力を見つけ常に新鮮であれば、どんなに「長い会話」でも決して退屈しないでしょうね。
例2
今日はおめでとう。
幸福な若いお二人の姿を眺めるのは、実にいいものです。
お二人の目が、輝き、潤み、幸せに酔っているようなものが誠によくわかります。
ここで、そのお二人の眼を見ていて、私は、あるドイツの劇作家の言葉を思い出しました。
それは、
「女は深く見る、男は遠くを見る」
という言葉です。
「女は近くを見る」ではなくて、「深く見る」です。
妻は、夫やわが子の心を深く読み取り、つかみ、操縦する天才です。
これは女性のもって生まれた才能でしょう。
男は常に先ばかりを見ています。
恋愛時代から、「この女性は、いつどういうふうに口説こうか」とか、「結婚後はどうしようか」とか、将来の設計を考えることが多いのです。
ときには妻が、手綱を引き締めないと、遠くばかり見ている夫はつまずきます。
一方、女性も「深く見る」ことが得意でも、見ることに愛情がなければなりません。
なぜなら「見えてしまう」ことも決して幸せなことではないからです。
愛情があってこそ深く洞察することが生きてくるのです。
このことを心得て、お二人とも調和した家庭を作ってください。
例3
嫌な言葉ですが、「結婚は恋愛の墓場だ」という言葉があります。
しかし、この言葉はこれとしてよいではないか、と私は思っています。
今日で、お二人の甘い甘い独身時代は終わります。
そして、もっともっと甘いハネームンが始まるのです。
「人生には、花も嵐もあるよ」とは、結婚式でよく言われる言葉ですが、私がお二人に言いたいのは「今までの恋愛は終わり」、そして、今度は「本当の愛情の誕生」ということです。
「夫婦愛」です。
本当の完成された意味での「男と女の愛の生活」がこれから始まるのです。
お互い人間ですから、いろいろなことがあるでしょう。
「燃え上がる恋」に酔っているときには解決できない問題も、愛し合い、信じ合っている夫と妻の「愛」ならば、解決できるのです。
お互いの真実の「愛」を確認できるのです。
その意味で、今までの「恋」は終わったと言えましょう。
フランスの作家サン・テグジェペリがいいことを言っています。
「愛するーーそれはお互いに見つめ合うことではなくて、一緒に同じ方向を見つめることである。
」これが「夫婦愛」です。
新しい愛のスタートを心からお祝いします。
おめでとう。
例4
結婚についてのことわざやアドバイスはたくさんあります。
多くは結婚に対する苦言や忠告で、こんな場所ではウッカリしゃべれない言葉ばかりですから、私も気をつけて話します。
ともかく結婚というものは、一つの区切りであり、同時に出発です。
恋愛時代は「アバタもエクボ」だった二人も、これからは現実に目を見開いて歩まなければなりません。
そこで、いろいろなことわざが生まれるのです。
失敗した連中、幻滅を感じた連中が、半分ひがんで言った言葉でしょう。
最近は女性上位の時代で、女性の言うことさえ聞いていれば世の中は平和だそうです。
たしかに女性は、母としてよき教育者であり、妻としては夫のよき操縦者です。
そうでなくてはいけません。
バルザックは、いいことを言っています。
「女はよき夫を作る天才でなければならない」と。
まさに、夫を立派に育て上げるのも、だめにするのも、妻であるということでしょうか。
そうなると、私が今日この状態であるのは妻の責任ということになります。
そうだと私も気が楽になったというべきでしょうか。
いずれにもせよ、妻はよき教育者にちがいないのです。
入社式でのスピーチ
例1
皆さんは、今日から新しい道を歩むことになります。
今までも、まったく違った道のようでありながら、決して違った道ではありません。
皆さんの、今までの「人生」の延長線上の道でもあります。
道の両側の風景は、今までとはガラリと変わるかもしれません。
すれ違う人も今までとは違います。
月並みな言葉で言えば、この道には、昼も夜も、晴天も、嵐もあるでしょう。
「これが人生なのだ」と、片づけてしまっては身もふたもありませんね。
作家の中島敦が、ドキッとするような言葉を言っています。
「人生は何事をもなさぬにはあまりに長いが、何事かをなすにはあまりに短い」。
私は、この言葉をはじめて聞いたときに慌てました。
「まだ、間に合うかな」と真剣に思いました。
「今まで、なんと多くの時間を無駄に過ごしてしまったのだろう」と。
とにかく、今の出発点からでも、皆さんの人生が長くなるか、短くなるか、改めて考えてください。
それによって、一生のあいだに何を得るか、または何を失うかが決まります。
人生にとって、何事も遅いことはないのです。
大切なのは新しい道を進もうとする決意です。
例2
アメリカのマーフィーという人は、経営上の名言といわれる言葉を数多く述べていますが、みんなごく当たり前のことを言っているのです。
「人生は、その人の心に思い描いたおとりのものだ。
楽しいと思えば楽しくなり、苦しいと思えば苦しくなり、豊かになりたいと思えば豊かになり、貧しく考えれば貧しくなる」
と説き、日常、そう考える潜在意識で生活をコントロールできることを強調しています。
一種のマインド・コントロールですが、これを活用すれば効果があることもあります。
「会社は集団だが、その集団で成功するには、自分の考えが集団的であってはならない」
という言葉も、逆説的な言い方ですが、面白い心理を含んでいます。
独創的で個性的なプラン、会社という集団にとらわれない考え方は、「会社人間」からは生まれてきません。
皆さんには、よい意味で「脱社会的」な、自由な発想を持ってもらいたい。
そして、常に会社に活力を与える存在になっていただきたいと、思うのであります。
活躍を期待します。
例3
この不況の時代に、皆さんは、この会社を選んで受けられ、そして入社されました。
いろいろな条件を考えての決断であったでしょう。
その決断が正しかったかどうかは、これからの行動によって、あなた方一人ひとりが決めることであります。
かつての、日本経済の高度成長期は、各人の能力がフルに発揮された時代でした。
しかし、今はそうではありません。
物事を着実に、正確にやり遂げなければならない時代です。
「平凡なことを、毎日平凡な気持ちで実行することが、すなわち非凡なのである」といったアンドレ・ジッドは、今日の経済社会を意識していたわけではないでしょうが、この言葉こそが、この経済界の「冬の時代」にぴったりしているようです。
バブルの夢を追った企業の結末は、ご承知のとおりです。
どうか皆さんは、新しい意識で、この時代を乗り切るための力を発揮してください。
私たちも、皆さんの期待を裏切らないように努力します。
そのためには、皆さんの力が大きな役目を果たすことになるでしょう。
期待しております。
例4
皆さんは、いよいよ社会人として今日から第一線で活動を開始されるわけですが、最近は学生時代からアルバイトなど社会の経済活動を経験されている方が多いので、新人としての心構えや教訓めいたことはお話しする必要はないでしょう。
ただ今後は、皆さんは「自分の懐」のためではなく社会人として働くので、お金に対する考え方がちょっと変わってくるかもしれません。
イヤ、変わらなくては困ることもあります。
アメリカの政治家ベンジャミン・フランクリンは、金銭について現実的な名言を多く残しています。
「金は良い召し使いでもあるが、悪い主人でもある」「ささいな出費を警戒せよ。
小さな穴が大きな船を沈めるであろうから」「もし、諸君が金の価値を知りたいと思うならば、でかけていって、いくらか借金を申し込んでみたまえ」
説明は要らないでしょう。
すべて金銭の価値、金銭に対する執着などを知り尽くしている人の言葉です。
ここまで知るためには何度も何度も失敗や成功の経験があるはずです。
皆さんも、金についての経験――それが良くても悪くても――を恐れてはいけないし、甘く見てもいけないと思います。
それが十分に生かされることを望んでいます。
朝礼・課会・部会でのスピーチ
例1
私たちが、社会人としても個人としても「信用があるかないか」「信用されているかどうか」というのは、人格の根本にかかわる大きな問題であります。
私たちは、第一印象で人を判断することが往々にしてあります。
「直感は信用できる」というが、果たして一目見ただけで、その人のすべてがわかるでしょうか。
「一目ぼれ」で信用できるかどうかは、決してわかりません。
あるいは一目見ただけで、ただ印象が悪いということだけで、信用できないと思うことも間違いです。
それではどうしたらいいか。
時間を掛けた「誠実」であります。
損得を考えない「誠実」です。
「誠実」こそ、相手の信用を得る、相手に信用を与える基本であります。
最も悪いのは、経済的な「駆け引き」で相手の信用を得ようとすることです。
古代ギリシアの政治家テミストクレスは,こんな言葉を残しています。
「金で信用を作ろうと思うな。
信用で金を作ろうと考えよ」
昔から、こういう手段で「信用」を勝ち得ようとした人がいて、また、それで手痛い失敗をしたことがあったのでしょう。
これこそ、事実に基づく教訓でありましょう。
心すべきことです。
例2
人間の社会というものは、どこでも上下関係が存在しています。
動物の世界なら、強いものが弱いものを力で押さえつけて優位に立ちますが、人間の社会でもこれに似た関係が多くあるのは、皆さんがご承知のとおりです。
ゴーリキーの有名な戯曲『どん底』の中の台詞に、こういうのがあります。
「仕事が楽しみなら人生は娯楽だ。
仕事が義務なら人生は地獄だ」
まさにそのとおり。
しかし、自分にできないことを他人に要求することがよくあるものです。
とくに上司は、ときどき、いや始終かもしれませんが、「そんなことできるもんか」、というような、無理を承知の上で困難な仕事を命ずることがあります。
私もしばしば、そういうことをしたかもしれません。
謝ります。
言われたほうは、「地獄」ですね。
ただし、言われたほうは、その仕事を完遂したときに、「やった」という満足感・優越感に満たされることでしょう。
命令したほうは、自分ではできなかったかもしれない困難な仕事を、命じられた人が成し遂げたことに対して素直に感謝すべきです。
そこに、会社という集団が発展する、調和と信頼の基礎が確立されます。
例3
「失敗は成功の母」という言葉は有名ですが、これはずいぶん安易な言葉だと思いませんか。
こんな気持ちで安易に失敗してもらったら、正直な話、社会は大変迷惑するのです。
失敗は絶対してもらっては困るのです。
しかし、人間である以上、一生のうち失敗することは必ずあります。
失敗は恐れてはならないのです。
作家・田宮虎彦の言葉に「青年の持つエネルギーは、傷つくことを恐れているようでは、何事もなし得ない」というのがあります。
人生のなかでは、闘わなければならないときがあります。
そのとき傷つくのを恐れて逃げ回っていたら、何もできないでしょう。
しかし、負けることがわかりきっているのに闘うこともないのです。
五分五分なら、少し冷静に考えて見ましょう。
四分六分の勝負なら、傷ついても勝つかもしれない。
そういうときに、皆さんならどうしましょうか。
本当のエネルギー、勇気はそういうときに使うためにあるものです。
頭を働かせたクレバーな闘いをしていただきたいと思います。
それが結局、勝利につながることは、いうまでもありません。
例4
皆さんは一ヵ月に何冊,本を読みますか.私の言っているのは週刊誌や漫画本ではありません。
ハードカバーの単行本です。
今は活字離れの時代といわれています。
テレビ、ラジオ、マンガなど、いわば視覚や聴覚に直接訴えるメディアが多く、活字を見る、文章を読み取ることによって思案する時間があまりにも少ないように思います。
仕事が忙しく、ものを考えたり、本を読んだりする時間が少なければ少ないほど、私は皆さんに読書を勧めたいのです。
イギリスの文学者ゴールド・スミスは「良書を始めて読むときは新しい友たちを得たようである。
前に精読した書物を読み直すときは旧友に会うのと似ている」といっています。
読書にはそういう喜びがあります。
もっと大事なことを、アナトール・フランスが言っています。
「私が人生を知ったのは、人と接触した結果である」
そのとおりだと思います。
良書によって、私たちは、まったく知ることのできなかった事実、出来事、教訓、人々に巡り会うことができます。
仕事を通じて生身の人間に会うことも大きな勉強ですが、どうか忙しい仕事の合間に良書と接触することをお勧めします。
定年退職者の送別会でのスピーチ
例1
長いあいだ、ご苦労様でした。
そして、本当にありがとうございました。
大先輩に対して「送る言葉」などと大それたことは言えませんが、井上靖さんの言葉で、私の忘れることができない言葉がありますので、それを申し上げます。
「年齢というものには元来、意味はありませんよ。
若い生活をしている者は若い。
老いた生活をしている者は老いている」
こういう言葉なんです。
説明はいりません。
「先輩の生活そのものである」といっても、おそらくこの席にいる人たちは、みんな納得するでしょう。
私たちはみんなお世辞ぬきでそう思っていました。
どうか今までどおり、若々しくお過ごしください。
そして「会うたびに、先輩は若くなりますね」と、いつまでも言われるようにお過ごしください。
私たちもいつまでも若さを失いたくないと思っております。
先輩を手本に生きてまいります。
お元気で。
○○○○○
○○○○○
例2
歳をとることを極端に嫌がる人がいます。
男でも女でも、誰でも年寄りになるのを喜ぶ人はいないと思いますが、とくに女性は年をとって「しわ」が増えるのを嫌がりますね。
しかし、これはさけれれない人間の運命です。
いつまでも若々しくて、ダンディーな人もいます。
その若さがちっともいやらしくないんです。
みっともなくないんです。
○○さんもその一人だと、私はずーっと思っていました。
とても定年などとは今でも信じられないくらいです。
さっきの「しわ」の話ではありませんが、有名なフランスの思想家モンテスキューが、こんなことを言っています。
「老年はわれわれの顔よりも心に多くのしわを刻む」
「心のしわ」は、誇るべきしわです。
それを人生の英知を語っている「しわ」なのです。
われわれは、その「しわ」の一つ一つに、大きな教訓と知識を学ぶのです。
○○さん。
どうか顔の「しわ」と一緒に「心のしわ」をもっともっと増やしてください。
そして私たちに貴重な経験を教えてくださるように、お願いいたします。
長いあいだ、ありがとうございました。
転勤者・退職者の送別会でのスピーチ
例1
「潮時」という言葉があります。
釣りをするにも、結婚をするにも、決断するときにも、必ず「時」があると思うのです。
私も、若いときから、その「潮時」を間違えては、何度も何度も失敗をしました。
取り返しのつかない失敗も、ありました。
アリストテレスがうまいことを言っています。
「宴会からと同じように、人生にも飲みすぎもせず、喉が渇きもしないうちに立ち去ることが一番よい」
これは人生の「潮時」についての言葉ですが、どんなにおいしいものも、うまい酒も、過ぎると毒になることがあります。
最もおいしいときに、サッと場所を変えて、別の食事や酒を楽しむのは賢明です。
それは、人生を楽しくし、視野を広め才能を発揮できます。
仕事についても同じことでしょう。
だからこそ何よりもまず、本当に必要な場所で、自分の仕事が思い切りできるのではないでしょうか。
新しいところで、新しい職場で、期待されているあなたの才能を思う存分出してください。
みんなで、喜んで、拍手をもって、あなたをお送りします。
例2
○○さん。
長年、お住みになったこの地を、たとえ数年間でも離れるということは、やはり寂しいものでしょう。
しかし、新しい土地の魅力もまた捨てがたいと思いますね。
風光・人情など、またこの土地とは変わった珍しさ、美しさがあるのではないでしょうか。
どうか仕事もさることながら、そっちの魅力のほうも十分に楽しんできてください。
私たちが出張するときは泊めてください。
今から予約しておきます。
冗談はさておき、ちょっと偉そうな顔をして、送別のことを述べさせてもらいます。
私の好きな山本周五郎の作品『ながい坂』の中にこういう言葉があります。
「人の人生は曲がり角だらけだ」
「なんだい。
当たり前じゃないか」といわれれば、たしかにそのとおりです。
サラリといってのけたこの言葉の「重さ」。
私は、「これぞ人生」と思います。
お互い曲がり角を曲がって露地を通ってまた巡り会う。
面白いものです。
○○さん。
今日のこの曲がり角で「しばらく、さようなら」と言いましょう。
そして、また、いつか、どこかの曲がり角で「やあ、今日は。
」という日を楽しみにしています。
表彰式・授賞式でのスピーチ
例1
よく、ある人を指して、天才とか才人とかいうことがあります。
しかし、厳密な意味で、本当の天才などそこら辺にいるわけがないのです。
大部分の人は普通の人で、いわば凡人というべきでしょう。
何かの賞をもらうということは、明らかに人より優れた才能の持ち主であるということです。
私たちは、ここに一人の優れた才能を持つ友人を得たことを、心から幸いに思います。
アメリカの医者でオスラーという人はこんなことを言っています。
「二十五歳まで学べ、四十歳まで研究せよ、六十歳までに全うせよ」
自分の経験から得た「研究年齢」のことをいっているのかもしれません。
「二十歳にして重きを成すのは意志、三十歳にして機知、四十歳にして判断」と説くのはフランクリンです。
いずれにせよ、年齢が人生に大きく影響し、生き方によっては、勉強の仕方によっては、大きく変わることを言っているようです。
あなたはまだお若いから、これからが楽しみです。
上手に、そして賢明に、計画的に年をとって、更に飛躍してください。
期待しています。
例2
賞というものは、どんなものでも、何度もらっても嬉しいものです。
とくにこの○○賞は特別で、そこにもここにもあるものではありません。
それだけに私たちもとくにあなたが選ばれて受賞されたことが嬉しいのです。
詩人キーツが、このようなことを言っています。
「耳に聞こえるメロディーは美しい、だが聞こえないメロディーは更に美しい」
賞の対象になったものは、もちろんすばらしく優れて美しいのですが、それを生み出したものは、さらにさらに美しく輝いています。
人をして感得させる。
この輝きは才能であり、知識でもあったのでしょう。
それは私たちが手にとって見られるものではないかもしれません。
しかし、「聞こえるメロディー」としての作品をつくり上げた才能や知識にもまして、この受賞に値するのは、○○さんの人間性にあったのだ、と私は思います。
多くの人が、その「聞こえないメロディーを」を聞き取り、知ることになったことは、実に嬉しいことです。
心からお祝い申し上げます。
○○○○○
○○○○○
例3
おめでとうございます。
あなたに、お祝いを申し上げるのはむしろ遅すぎたぐらいです。
もっともっと早く、この機会があってもよかったと思っています。
ただ、ある言葉を思い出すと「ああ、これでよかったんだ。
神様は、ちゃんと期待を考えてくださったんだな」と思います。
それはこういう言葉です。
「世の中のことは何でも我慢できるが、幸福な日の連続だけは我慢できない」
これは、かのゲーテが言った言葉です。
何も望むことのない日々の連続ほど退屈なものはないでしょう。
いくらか逆説的な意味を持つこの言葉は、精神的にも絶えず満たされていることが決して本当の幸福ではないことを言っています。
ハングリーであるほうが、人間は幸せであるともいえます。
賞を得るのが遅かったあなたは、幸福な毎日を過ごすことができたわけです。
お祝い申し上げます。
○○○○○
○○○○○
告別式でのスピーチ
例1
人間は、必ずいつかは死にます。
太古の昔から何億回となく繰り返されてきた悲しみなのに、死を前に私たちの悲しみは、決して薄らぐものではありません。
人間の歴史の長さから考えれば、人の一生はほんとうに夢のようです。
偉い僧侶の人たちが、人生のはかなさを何度も何度も説いているのが分かりながら、愛する人との別れは、常に苦しく、悲しいものです。
今私は、ここあなたの柩の前に立って、フローベールの一つの言葉を思い出しています。
「友人の死――それはあなたの中の何ものかが死んだことである」
そのとおりなのです。
今私は、私の人生でもっとも大切なものを失った悲しみを感じています。
ただ唯一の慰めは、皆さんの心の中にあなたの残されたものが、脈々としてこれからも行き続いていく、と思えることです。
悲しみをこらえて、あなたの残された数々の愛・教え・思い出を、私たちは決して忘れないでしょう。
どうか見守っていてください。
さようなら。
○○○○○○
○○○○○○
例2
死という誰にでも訪れる厳粛な事実の前には、言うべき言葉がありません。
死というものについて述べても、死後の世界について想像で話してみても、今深い悲しみの底にあるご遺族の方たちにとっては、何のたしにもならないのです。
ただ故人は、いまや肉体的にも精神的にも、すべての苦しみから完全に解放されていることだけは確かでしょう。
それが、悲しみにある私たちの、たった一つの慰めです。
いまここにギリシアの詩人アンティバネスの詩を捧げましょう。
「友を失うことを、あまり嘆かぬがよい。
死んでしまうたわけでなく、我らもみんな、い