マナー教育の必要性と教育者の役割Word格式.docx
《マナー教育の必要性と教育者の役割Word格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《マナー教育の必要性と教育者の役割Word格式.docx(16页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
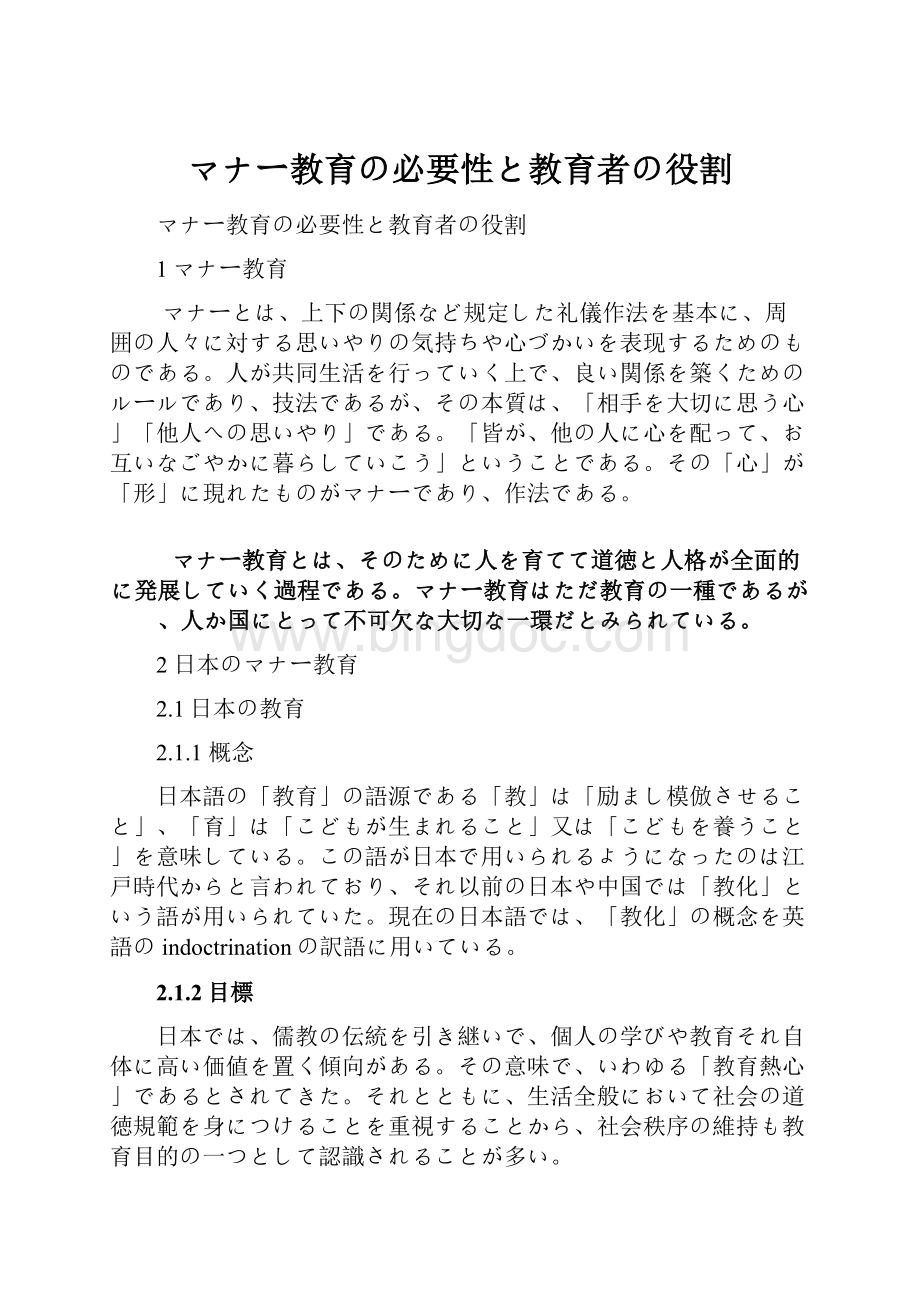
第二次世界大戦後の教育は、日本国憲法と教育基本法に基づいている。
2.2日本のマナー教育の内容
行われる場に応じて家庭のマナー教育、学校のマナー教育、社会のマナー教育の3つに大きく分けられている
2.2.1家庭のマナー教育
Ⅱ.マナーをめぐる三層構造論社会・歴史的背景
日本文化におけるマナーの形成について熊倉(1999)は第一の層は、もっとも基本的な層で、人類に共通のレベルにかかわる層でもあり、動だと解される。
例えば、ガンの雌雄がつがいとなる際レベルにかかわる層でもあり、おそらく進化論的なメカニズムや宗教的な背景があるとえられる。
には、互いに羽を広げ、首を高く伸ばして敵を威嚇するニズムや宗教的な背景があるとえられる。
縄張りを作る動物の多くが、自の縄張りにつがいとな
る相手を導入する際に求愛行動の挨拶として攻撃行動をとることを示した。
これは、つがいとなる相手と自がは、歴的に三つの層から成るモデルを提案している(図協同して縄張りに侵入する敵を追い払うという象徴的行1)。
第一の層は、もっとも基本的な層で、人類に共通の動だと解される。
例えば、ガンの雌雄がつがいとなる際レベルにかかわる層でもあり、おそらく進化論的なメカには、互いに羽を広げ、首を高く伸ばして敵を威嚇する第二の層は、時の警告音を発することが婚姻の合図となる。
ヒトの挨武士社会の行動様式を規範として江戸時代に完成された拶行動の一つである笑顔も同様に歯を剥くという動物と日本の伝統的な礼儀作法にまつわる層である。
そして第共通の攻撃行動に源があるという。
そのために、他者が三の層は、明治以降、近代化により導入された西欧流の自に向かって見せる笑いが時として、笑われる行動規範に大きく影響された礼儀作法の層であり、異文という脅威の意味にもなる。
化の衝突により形成された新たな文化的背景をもつものヒトの新生児は、生まれた直後からムシ笑いをするよとえられる。
本論では、熊倉(1999)の案を参にして、現代におビョークランド・ベレグレーニ無藤隆志(監訳)
D.F.A.D.
ける個人内のマナー形成を四層からなるモデルを土台と(2008)進化発達心理学ヒトの本性の起源P6現代青年のマナー観について(佐々木)27
図1マナーの形成層(熊倉功夫(1999)より)
注)熊倉(1999)より筆者が図式化、作成
うに遺伝的にプログラムされている。
それが、母親の乳につけることに重きを置き、簡素で美しく無駄のない動児に対する親愛の情を高め、細やかな働きかけを引き起きが尊ばれた。
こうした動きが後に、茶道における洗練こすシグナルとなり、乳児の生存率を高くする。
この働された所作の体系化へつながったといわれている。
きかけ(声をかける、目と目を合わせる)は、また、ヒ江戸時代に入ると、家の躾は武家の教育を基におこトにとって不可欠な言語の獲得にも重要な役割をもつこなわれるようになった。
当時、身や階層によって習慣とが知られている。
が異なっていたことは周知のことであるが、いわゆる町このように、第一層である古層の基本的なマナーであ人の間でも武士階級の礼儀作法(マナー)がひとつの基る笑顔は、獣との類似行動をもとにして始まったもので準とされたのである(池上2005)。
男子に対しては、文武あるが、その後徐々に社会的場面で意図的に用いられるの修業の他、日常の礼儀作法・言葉づかい・物事の取りようになっていくとえられる。
さばき方(山川1983)など、また、女子は実生活に必要
な読み、書き、裁縫の技術習得や武家邸、商家への行儀
ところが学生を見るに、彼女らは家庭でも学校でもマナー教育らしいマナー教育を受け
てこなかった。
マナーには必ず、そのような「形」がとられる「理由(こころ)」がある。
学生は「形」も十分に教えられていないし、ましてや「理由」を教えられていないので、
1どうすれば良いのか、なぜそうしなければならないのかが分からない。
本論は、若者のマナーが何故このような危機を迎えてしまったのか。
このような事態を前にしてマナー教育はどうあるべきかについて考察するものである。
マナーはそれぞれの時代に適応しながら、世代から世代へ継承されていくものである。
社会の急激な変化によりマナーのあるべき姿が変容しつつある中で、今や我が国では、若者を教育すべき立場にある世代自体がマナーの真の意味を見失い、次代に伝える術を失っている。
そこに問題の本質がある。
以下の章で、筆者は、教育者が学習者と共にあるべきマナーやマナーの意味を探索し、そして実践することが必要ではないかということを問題提起し、また、その方策について考察を行うつもりである。
2.マナー教育の日本的特質
言葉を覚えたチンパンジーとして有名な犬山・京都大学霊長類研究所のアイが、初めての子どもアユムの子育てに励んでいる姿がNHKテレビ3)で紹介された。
その姿に学習というものの本質を見ることができる。
アイは自分がコンピュータ学習をしている姿をアユムに見せるが、決してアユムの手を取って教えることはない。
アユムは母親の姿を懸命に観察しながら真似ようとする。
まさに「学ぶ」は「真似ぶ」だといわれるそのままの姿である。
チンパンジーがアブラヤシの実を石で割る文化の継承について、アフリカ・ギニアのボッソウ村で観察された姿もそのようなものであった。
「模倣」が日本の「学び」の伝統であると辻本雅史はいう4)。
また、東洋(あずまひろし)は日米の育児を研究して、アメリカの母親が「教え込み型」育児であるのに、日本の母親は「滲み込み型」育児であるという5)。
アメリカの母親が、言葉による分析的で組織的な教え方をするのに対し、日本の母親は、言葉で意味や理論を理解させるよりも、直接自分でやってみるといった実践的な教え方をすると言う。
なぜそうなったかについての筆者の推論はここでは措くとして、日本の家庭教育は、霊長類が獲得した子育ての方法の自然な延長線上にあると考えられる。
一方、アメリカの家庭教育の方法は、そのまま学校教育の原理につながっている。
東によれば、「教え込み」は、基本的に子どもは教えられることによって学ぶという前提に立つ。
そして、<教える−教えられる>という関係をつないでいる手段は「言葉」である。
これに対し、「滲み込み」は、模倣および環境の持つ教育作用に依存する。
環境が整っていて、よいモデルがあれば、子どもは「自然に」学ぶという前提に立つ。
辻本雅史は「滲み込み型」教育モデルが、日本のほとんどあらゆる伝統的な学びの場において、教育や学習の原理として生きていたと主張する。
また、本来「教え込み型」の方法を原理としている現代の学校教育の中に、気付かないまま「滲み込み型」学習文化の伝統が生きていると主張する。
辻本は、近世前期の儒者貝原益軒の学問と思想の中に「滲み込み型」の教育思想がはっ
2きりと語られていると言う。
益軒は「予(あらかじめ)する」という言葉で、子どもが生まれて悪に移ってしまう前に、早く子どもに教えなければならない、という一種の「早期教育」を主張した6)。
また、子どもが「見ならい、聞きなら」って、それに「似する」という過程、いわば子どもの模倣する力こそ、人間形成の決定的な要因であると指摘している。
そして、「教える」ということは、何事かを積極的に教え込むことではなく、実際には良くないことをすれば「戒める」ということによってなされる。
子どもは自らの活動を通じ、「見ならい、聞きなら」いながら、自力で学んでいく。
そのためには、学ぶ側に学ぼうという「立志」がなければならない。
また、教える側(師匠)は「子どもの見ならう所の手本」でなければならない。
益軒の教育においては、子どもが自らする模倣と習熟の過程こそが重要である。
「見ならい、聞きならい」する活動が、無自覚な習慣になるまで繰り返されることによって、身の内にしっかりと滲み込む。
つまり、言葉による意識の回路を通さない、言葉によって意識化される知とは異なる、ある種の「身体知」の獲得を目指しているといえる。
益軒は、人間社会における、人の「他者」に対する正しい関わり方を、「礼」として、「日常に即した身体作法」として説く。
心を正しくするためには、外に現れたさまざまな身体上の規律を、「礼」として、日々実践することが重要であると説く。
辻本は、この「身体の規律化」「身体から心へ」の方法原理が、家庭教育ばかりでなく、日本の学校における「校則」の根底にあり、学校教育の目的である「知育」と「徳育」の、後者を支えるものとしての位置づけを担ってきたと見る。
また、この「滲み込み型」の原理が、権威主義を嫌う、教師と子どもの「友達関係」に影響してきたと見る。
3.マナー教育の崩壊
ここに来て、疑問が生じてくる。
現在の日本の親たちが、教師たちが、そして職場の先輩たちが、マナー教育において、「滲み込み型」教育の良き模範となっているだろうか、「教え込み型」教育に必要な「言葉」を持っているのだろうか。
また、教わる側の子どもたちに「立志」があるのか、人生の先輩たちを模倣の対象と見ているのだろうか。
さらに、先輩から引き継いできたマナーそのものが、グローバル化の嵐の中で、そのチェックに耐えられるのだろうかと。
ここでまた、冒頭の座り込みの問題に帰ってみる。
筆者は本学併設高校の若い教員と食堂や連絡会、時には飲み会などで話をするので、この件について意見を聞いてみた。
「そんなに悪いことですかねぇ」という人がいる。
彼女らも邪魔になったら立つでしょうし、最近は廊下も道もきれいですからね」と言う。
生徒の髪の色についてもそうだ。
確かに、校則では染髪禁止になっているが、このご時世では髪の毛まで余りうるさく言えない」とのことだ。
彼らも遅刻やタバコなどについては厳しくチェックしているようだが、規律というものに対する意識がずいぶん違うのだ。
若い教師たちを観察していると、箸やペンを正しく持てない人がいる。
3日本経済新聞に「職員室」というコラムがあるが、そこでも教師自身の口から、教師の服装の乱れや、教師が自分の子を休ませて行楽に行った話などが語られている7)8)。
日本も高度成長期までは、家族がそろって食事をすることは普通だった。
テレビもまだ普及しておらず、その日の出来事を話しながら食事をした。
食事が終われば、家族が皆同じ部屋で団らんをしたり、子どもたちはちゃぶ台で宿題をした。
子どもの数も多く、兄弟姉妹で一つの社会ができた。
そこでは、親から子へ、兄から弟へ、「滲み込み型」のしつけ教育があった。
それが、高度成長期以降は、家族はすれ違い。
食事もバラバラで、たまに一緒にしても、目はテレビに釘付けで、ろくな会話もない。
食事が終われば、子どもは子ども部屋に引きこもってしまう。
そんな家庭が多くなった。
「滲み込み型」しつけができる環境ではなくなった。
では、学校でそれを補うしつけ教育があったかというと、徳育のための十分な教科もなく、教条化した校則による締め付けがあっただけだ。
今の若い親や教師たちの成長期は既にそんな時代に突入しつつあった。
きっちりした「しつけ」を受けていなければ、子どもにきっちりした「しつけ」をすることは難しい。
もちろん、そんな中でも立派なしつけを受けた人も多い。
しかし、その人たちも、子どもから、どうしてそうしなければいけないのかを問われたとき、説明できる言葉を持たない場合が多い。
子どもの側も年長者を今や模倣の対象と見ていない。
彼らの模倣の対象は商業主義に侵されたテレビ画面上の仮想現実である。
日本には小笠原流礼法や、茶道など立派なマナー教育の伝統があるにも拘わらず、それらは今や、企業研修や就職対策教育、冠婚葬祭マナーなどの箱庭の世界に閉じこめられ、日常生活の中に根付いていない。
その上に、グローバル化の波である。
海外との交流の必要から国際儀礼(プロトコール)修得の必要性が叫ばれる。
日本の伝統作法とプロトコールの断片的知識がぶつかり合い、混乱している。
しかも、「形」のみが一人歩きし、「こころ」が忘れられている。
接客のアルバイトで与えられる奇妙なマニュアルが学園までも汚染している。
マナー教育の崩壊である。
マナーおよびマナー教育の崩壊については、さまざまの原因が語られている。
おそらく、それらのほとんどが真実であり、複合汚染なのだろう。
しかし、その大きな原因が教える側にも存在するとすれば、マナー教育を復権させる方策はあるのだろうか。
また、若者にマナー学習への「立志」がないように見える。
「立志」は、本来外部から強制されてできるものではない。
若者の中に「立志」を内発させる工夫はあるのだろうか。
4.マナー教育の復権
学ぶ側の「立志」ということに関して、稲垣佳世子と波多野誼余夫の日常的認知からの研究がある9)。
両氏によれば、伝統的学習観では学び手が受動的な存在であり、しかも有能でないという仮定をおいているが、日常認知研究から見た新しい学習観では、子どもはもっと能動的で、有能な学び手である。
意味のある課題に取り組む中で、技能に習熟する
4ばかりでなく、概念的知識をも獲得していくとする。
「教え込み型」と「滲み込み型」に相似する考え方といえる。
しかも、益軒が「立志」を問題としているのに対し、両氏は、より積極的に、それが始めから子どもに備わっているものとして、その能動性や有能さを引き出す教育を提唱している。
両氏は、その方法として、子どもが学ぶべき事柄に関して既有知識を持っている場合は、「まちがうことを尊重する」「探索することを奨励する」「子ども同士のやりとりをうながす」などの方策を用い、既有知識を持たない事柄に関しては、「媒介物による日常生活化」によって具体的イメージを持たせ、また、「教師も答えのわからない問題に取り組む」ことによって、教師も生徒も一体になって活動に打ち込むことを提唱している。
そして、その際重要なのは、教師の「教育的創造力」であるとしている。
筆者は両氏のこの理論が、短期大学におけるマナー教育において大いに参考になると考える。
「立志」に関して言えば、最近の学生はマナーに無関心に見えるが、適当なきっかけがあれば関心を寄せるのではないかと考える。
就職活動はそのきっかけになりうる。
普段マナーを拒絶している学生も、就職活動のためということであれば、マナー教育を受けることに納得する現状がある。
これを利用して、就職活動を契機として、学生生活も含めた日常生活に必要なマナーについて、学生自身にその大切さを気付かせ、能動的に学習させることが可能なのではないかと考える。
つまり、「就職活動のためのマナー教育」ではなく、「就職活動を契機としたマナー教育」ということである。
また、学習の方法に関して言えば、マナーにも、学生が自身の日常生活から類推して、どうすべきか判断がつきやすいもの、かなり人生経験のあるものでも容易には判断のつきかねるものなど、いろいろある。
事柄によって学習の方法は変わってくるはずである。
もはや、理屈抜きで体に覚えさせる完全な「滲み込み型」教育は難しい。
参加型学習法などで、学生がその日常生活から判断のつきやすい問題については、教師はファシリテーター(森良は産婆役と定義づけている10))に徹し、学生自身の気づきに任せればよい。
しかし、判断の難しい問題については、教師も学習者として積極的に参加するなどの工夫をすることが有効であろう。
特に、社会状勢の急激な変化により、伝統的マナーがその有効性を失っていると考えられるような事柄や、国際プロトコールを考慮しなければならないような事柄については、教師も学生も相当の下準備をして学習に参加しなければならないだろう。
いずれにせよ、参加型教育を主体にしつつ、時には「教え込み型」教育も併用する必要があろうが、そのためには、教師は学生を納得させるだけの明瞭な言葉を獲得しておかねばならない。
現在の教師は、不十分ながらも前の世代から「滲み込み型」教育を受け、ある程度のマナーを獲得し実践している場合でも、それを次世代に引き継ぐべき言葉を持っていないからである。
マナー教育は、もちろん、社会全体で行うべきものであるが、少なくとも短期大学において、どのような実践があり得るか、次にいくつかの事例を通して考えてみよう。
55.事例
(1)電話の切り方
非常に単純で、学生の日常経験からすぐに答えの出せる問題から始めたい。
電話を切るのは、かけた方からか、受けた方からか、ほとんどの学生はこの単純な問題にもマナーがあることを意識していない。
学生は頻繁に携帯電話を使っているが、この質問を受けて、即座に明確な答えを出せる学生は少ない。
「じゃあね∼」「じゃあね∼」と挨拶を交わして無意識に切っているが、どちらが先に切るかは、どちらが急いでいるか、どちらがせっかちかによる場合が多い。
中には、そう言えばかけた方から切っていると答える学生もいるが、その理由を問うと、かけたのはこちらだからと答えにならない答えが返ってくることがほとんどである。
しかし、しばらく学生同士に話をさせてみると、「用件が終わったかどうか、分かるのはかけた方だから」とか、「まだ他にも話があったのに、話の切れ目に、受け手が先に切ってしまって困ったことがあった」と言う学生が出て、皆が納得の境地になる。
この間、教師が話に介入する必要はほとんどない。
せいぜい、それではかけ手はどんな話し方をすれば、受け手がせっかちに切ってしまうことを防ぐことができるか、問いかけてやればよい。
そうすると又、学生たちから「電話の最初に、いくつ用事があるかを言っておけば良いのではないか」とアイデアが出てくるはずだ。
このように、学生の日常経験から推測できるような問題については、学生同士で話をさせると容易に正しい答えが出てきて、なぜそのようなマナーが生まれたのかを納得させることができる。
しかし、マナーはそのようなものばかりではない。
我々も少し深く考えてみないと人を納得させる言葉を見出せないものもある。
次にまた、廊下での座り込みの問題を取り上げてみる。
(2)廊下での座り込み
過日又、本学でひどい例を見かけたのだが、廊下で学生たちが車座で座っていた。
よく見ると、なんとコンビニの弁当を広げて食べていたのだ。
筆者は近づいて「君らは汚いことをして…。
そこは私が先ほど犬の糞を踏んだ靴で歩いていたところだよ」と言った。
学生たちは「ウソ!
」と叫んだり、「先生に注意されたのは3べん目だ」などと笑ったりしながら、なんとか立ち上がった。
筆者も急いでいたのですぐその場を離れ、廊下を曲がり際に振り返ると、学生たちはやれやれとばかり、また座り込んでいた。
筆者の注意を悪い冗談としか受け取っていなかったのだ。
そこで、別の学生たち対象であるが「秘書実務」の時間に、この問題について話し合ってみた。
「食堂まで遠いから」とか、「食堂が混んでいるから」別に良いじゃないかと言う学生も少数いたが、やはり、「廊下はきれいに見えても汚い、トイレに行った靴で歩いているのに」とか、「歩く人の邪魔になるからいけない」という、まっとうな意見が出てきて、やめるべきであるという結論に達し、筆者も胸を撫で下ろした。
そして、「廊下はあくまで、歩く場所だ。
教室と教室を結ぶ通路だ。
道路交通法でも、第76条4項で『何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない』として『道路において、酒に酔つて交
6通の妨害となるような程度にふらつくこと。
道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまつていること。
交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること』などが禁止行為として定められている」と解説をして終わった。
しかし、筆者は実はこれだけではどうも納得できない思いを持っていた。
筆者が心情的に学生の廊下での座り込みを許せないのは、単に不潔だから、通行の邪魔になるからだけだろうか、どうもそれだけではないという思いがあり、今少しこの問題を分析してみることにした。
その結果、結論に達したのは、廊下で座り込む姿は、学校で勉強をする心構えをつくるための身体のあり方(身体規律)から余りに遠いということである。
何事をするにも、その心構えが必要だということは誰も異論がないだろう。
その心構えをつくるのは身体である。
小笠原流礼法では姿勢のことをやかましく言う(「胴作り」という)。
筆者は服装や化粧など身だしなみも含めた、辻本雅史の言う「身体規律」が大切だと考える。
筆者はそれを「心構え」に対比して「身構え」と呼ぶと語呂がよいと思う。
(「身構え」を角川国語事典でひくと「敵・相手に対してとる攻撃・防御の姿勢・態度」と出てくるが、物事に対する姿勢・態度という意味でこの言葉を使いたい)。
講義と講義の間の休憩時間は次の講義に移るための準備の時間である。
廊下に座り込んでしまうのは決して準備の姿勢ではない。
学校に勉強をしに来ている限り、勉強をするための「身構え」「心構え」が欲しいのである。
このことは、学生の学校における身だしなみについての考え方にも関係してくる。
次にその点について検討してみる。
(3)学校における身だしなみ
服装を変えたときの気分の変化については誰しも身に覚えのあることだろう。
それだからこそ、制服というものがあり、逆に、ビジネスマンの制服たるネクタイ・背広を禁じるカジュアルデーの登場などがあるのだ。
本学は一応制服を定めているが、普段の通学については自由である。
従って頭のてっぺんからつま先まで様々で、驚くような姿も散見される。
これについては、授業の中でなかなか学生同士の討論は難しいので、まだ実現していない。
学生同士では遠慮があるからである。
そこで、個別に話をしてみると、自分はそんなに極端な姿をするつもりはな