日本戦国时代関ヶ原の戦い.docx
《日本戦国时代関ヶ原の戦い.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《日本戦国时代関ヶ原の戦い.docx(28页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
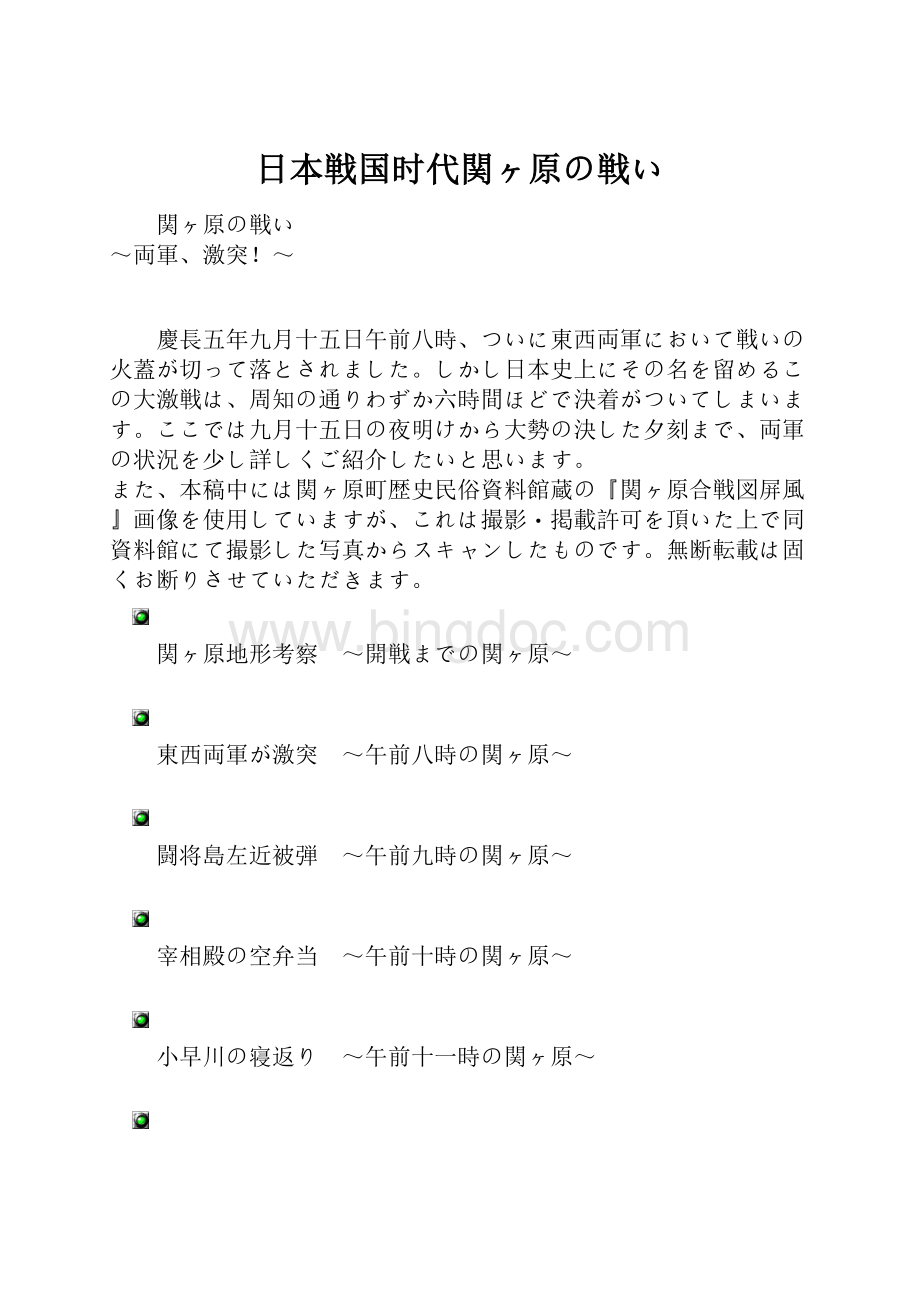
日本戦国时代関ヶ原の戦い
関ヶ原の戦い
~両軍、激突!
~
慶長五年九月十五日午前八時、ついに東西両軍において戦いの火蓋が切って落とされました。
しかし日本史上にその名を留めるこの大激戦は、周知の通りわずか六時間ほどで決着がついてしまいます。
ここでは九月十五日の夜明けから大勢の決した夕刻まで、両軍の状況を少し詳しくご紹介したいと思います。
また、本稿中には関ヶ原町歴史民俗資料館蔵の『関ヶ原合戦図屏風』画像を使用していますが、これは撮影・掲載許可を頂いた上で同資料館にて撮影した写真からスキャンしたものです。
無断転載は固くお断りさせていただきます。
関ヶ原地形考察 ~開戦までの関ヶ原~
東西両軍が激突 ~午前八時の関ヶ原~
闘将島左近被弾 ~午前九時の関ヶ原~
宰相殿の空弁当 ~午前十時の関ヶ原~
小早川の寝返り ~午前十一時の関ヶ原~
大谷吉継自刃 ~正午の関ヶ原~
西軍、総崩れに ~午後一時の関ヶ原~
島津の敵中突破 ~午後二時の関ヶ原~
関ヶ原地形考察
~開戦までの関ヶ原~
--------------------------------------------------------------------------------
時は16世紀最後の年、まさに「世紀の決戦」となった関ヶ原の戦い。
戦いを述べる前に、関ヶ原一帯の地形や交通路、両軍武将の布陣場所について少しご紹介します。
--------------------------------------------------------------------------------
関ヶ原パノラマビュー(松尾山頂から撮影)
「関ヶ原」とは
関ヶ原合戦が行われたのは、現在の岐阜県不破郡関ヶ原町一帯である。
地図を御覧いただけば判るが、北西には近江との国境に標高1377mの伊吹山があり、その山脈は関ヶ原一帯の北を東へ順に相川山・額堂山・金生山と続く。
この山脈東端の金生山は、家康が戦いの前日まで本陣としていた赤坂岡山(勝山)の北側に位置する山である。
また西には標高308mの城山とその東麓に小西行長・宇喜多秀家がそれぞれ布陣した天満山の北・南峯があり、南には小早川秀秋の陣した標高293mの松尾山がある。
南東には標高419mの南宮山があり、ここには毛利勢が陣を敷いた。
そして南宮山頂から北西へ2km下ったところに家康が最初に陣を置いた桃配山がある。
つまり、戦場となった関ヶ原一帯は、これらの山々に囲まれた、東西約4km・南北約2kmほどの盆地である。
関ヶ原中心部では東西を結ぶ中山道から北西へ通じる北国街道(越前街道または中筋ともいう)、南東へ通じる伊勢街道(牧田街道)がそれぞれ延びており、中山道は現在の国道21号線、北国・伊勢街道は国道365号線となっている。
ただ、旧伊勢街道は関ヶ原から烏頭坂を経由しており、R365よりやや東寄りの道である。
上の写真は小早川秀秋の陣所・松尾山上から撮影した3枚の写真を合成し、関ヶ原古戦場が一目で鳥瞰できるように作成した特製の画像である。
こうして見てみると、松尾山は戦況を一望の下に把握できる「特等席」であったことが実によくわかる。
やはり現地取材から得られるものは多大である。
西軍、布陣完了
西軍勢は九月十四日夜、大垣城本丸に福原直高、以下熊谷・垣見・木村・秋月・相良・高橋ら七千五百を留守として出陣、石田三成・島津義弘・小西行長・宇喜多秀家の順で関ヶ原へと向かった。
当時風雨が激しかった上に松明をも使わず、ただ栗原山に見える篝火(長宗我部陣のものか)を目標として行軍したという。
軍勢は野口・牧田の村落を経て山中村(関ヶ原西部)に到着したが、三成は途中栗原山麓の長束正家と松尾山小早川秀秋の陣所に立ち寄っている。
なお、この時四番手宇喜多隊の最後尾が東軍の一番手福島正則隊の先鋒と接触するという出来事があり、若干の損害を出した記録があるが、大きな戦闘には至らなかったという。
さて、西軍は直接関ヶ原の各陣地へ向かったのではなく、一旦大谷吉継陣所付近の山中村(現在のR21藤下バス停の北一帯)へと集結した。
これは吉継が西軍全体の参謀格であることを示していると思われ、ここで偵察を出して東軍の進軍状況を確認しながら軍議を開き、それぞれの持ち場(陣地)を決定した。
すなわち、笹尾山に三成、小池村に島津、北天満山に小西、南天満山に宇喜多と決まり、三成・島津は天満山の裏手から北上して藤川を渡り(当時は樵道があった)、それぞれの陣地へと向かったのである。
すなわち、三成は小関村笹尾山に本陣を据え、その二町東(約220m・ここは小池村に入る)に二重の柵を設け、そこに島左近と蒲生備中らを配した。
そして三成本陣の北西山麓には織田信高と大坂弓銃隊(黄母衣衆)が陣したと記録にあるが、当時北国街道より北は一面の原野だったため、その詳しい場所は判っていない。
写真は現在の笹尾山で、あまり高い山ではないが関ヶ原を一望の下に見下ろせるため、軍の指揮には適した場所である。
写真クリックで三成本陣から戦場を望んだ画像へとリンクしてあるのでご参考までに。
次に島津義弘は小池村神田に本陣を据え、一町半(約160m)程せり出して甥の豊久と山田有栄が布陣、義弘本陣脇には阿多盛淳が並ぶ。
また小西行長は島津陣西側裏手の天満山北峯(北天満山)へ、宇喜多秀家は天満山南峯(南天満山)へそれぞれ布陣した。
大谷吉継は藤下村藤川台に戸田重政・平塚為広らと中山道を押さえる形で布陣したが、吉継は小早川秀秋の挙動に強い不信を抱いており、これは松尾山の小早川勢に対するものであったと思われる。
大谷陣から中山道を挟んで東南松尾山方向の藤下村平野(平山)には吉継指揮下の脇坂安治・朽木元綱・小川祐忠・赤座直保が一列に並んで布陣する。
後に彼らは小早川秀秋の寝返りとともに一斉に大谷勢へ襲いかかることになるのだが、この時点で吉継はそんなことは夢にも思わなかったことであろう。
東軍、布陣完了
一方、東軍勢は同夜西軍が大垣城を出たという情報を得ると、すぐに出陣の準備を行った。
一番隊の先鋒は福島正則で、午前二時頃赤坂を出陣した。
そして関ヶ原の西寄り・中山道南側の松尾村大関「関ノ明神ノ森」を背に宇喜多秀家の南天満山に対する形で布陣、続いて加藤嘉明・筒井定次・田中吉政は順次中山道の北に、さらに藤堂高虎・京極高知は中山道の南・柴井(現関ヶ原中学校付近)にて小早川・大谷勢に対する形で布陣した。
これらは東軍の左翼勢である。
二番隊(右翼勢)は黒田長政・加藤貞泰・竹中重門・細川忠興・稲葉貞通・寺沢広高・一柳直盛・戸川達安・浮田直盛らで、黒田・加藤・竹中は岡山(丸山)の麓に布陣して石田隊に対峙、他は中山道の北・中筋(中央部)に南北に並び、島津・小西隊と向き合う形となった。
三番隊(中央勢)は井伊直政・松平忠吉・本多忠勝および寄合衆と呼ばれる混成隊によって形成され、本多忠勝は十九女池(つづらいけ)の西、伊勢街道東側に桑山直晴兄弟・山名禅高・平野長泰らを従えて布陣、南宮山方面の敵が伊勢街道から関ヶ原に侵入してくるのに備えた。
井伊直政は茨原(現THK岐阜工場敷地内)に陣し、少し下がって松平忠吉がこれに並ぶ。
その北側には寄合衆四隊が続くが、その中には赤井忠家父子・別所重治・亀井茲矩・三好為三・兼松正吉らの名が見える。
南宮山方面の敵に対しては池田輝政が御所野に、浅野幸長が垂井一里塚にそれぞれ陣し、ここから野上村(関ヶ原東部)までの中山道の左右には、山内一豊以下中村・生駒・蜂須賀・有馬らが控えた。
これらは南宮山の敵に備えると同時に、万一の際に家康の退路を確保する役割があったと見て良いかと思う。
また、大垣城の押さえとしては西尾光教・水野勝成・津軽為信・松平康長が、赤坂の留守は堀尾忠氏がそれぞれ務めた。
家康は初め桃配山(現関ヶ原町大字野上字南桃配)に本陣を据えた。
十五日午前七時頃であったという。
「初め」というのは、家康はこの後二度陣を移動しているからで、その場所については後述する。
写真は現在の桃配山であるが、こちらも笹尾山同様に高い山ではなく、「丘」と言った方が適切である。
これも写真クリックで家康本陣から関ヶ原方面を望んだ画像へとリンクしてあるのでご参考に。
本陣の前備えには奥平信昌以下、牧野・大久保(忠佐)・高力・丹羽(氏次)・内藤ら、一段下がった中央に松平重勝・親正ら、右に酒井重忠・永井直勝・青山忠成、左に西尾吉次・阿部正次・酒井忠利といった面々が控える。
そして仮の武者奉行を西郷家員が、床几代を本多正純がそれぞれ務め、後備えには本多康俊・重政らが遊軍勢の酒井家次・本多忠政・遠藤慶隆らとともに控えた。
両軍の布陣が完了、早暁から立ちこめていた霧も晴れ、刻々と時間が経過し緊張が高まってくる。
そして・
東西両軍が激突
~午前八時の関ヶ原~
--------------------------------------------------------------------------------
九月十五日午前八時、福島勢が宇喜多勢に攻め掛け、ここに戦いの幕が切って落とされました。
西軍もこれを迎え撃ち、がっぷり四つに組んだ戦いが展開されます。
--------------------------------------------------------------------------------
名物家臣・可児才蔵
東軍の先鋒福島正則は、斥候に出していた祖父江法斎らから西軍の各陣の形勢などの報告を受け、家老福島丹波治重(のち正澄)に命じて宇喜多陣へ弓鉄炮を発せしめた。
宇喜多勢もこれに応じたが、未だ本格的な戦いは始まっていなかった。
そこで家康は井伊直政に伝令を派遣、松平忠吉を補佐して戦いを始めるよう命じた。
つまり、戦闘開始のきっかけを作らせたわけである。
直政はこれを受けて忠吉とともに前進、福島隊の前へ出ようとしたが、正則の侍大将可児才蔵に止められた。
才蔵曰く、「今日の先鋒は我が主正則である。
戦が始まるまでは誰一人通してはならんと申し渡されております」。
直政曰く「こちらは家康公の四男忠吉公である。
本日は初陣につき敵情を偵察していただこうと思い、私が付き添って斥候として出てきたまでである。
抜け駆けではない」
才蔵は忠吉の名に気後れしたのか、やむを得ず道を開ける。
すると直政らはそのまま進み出て宇喜多勢へ発砲したため、驚いた正則は全軍に攻撃命令を出した。
これにより福島隊と宇喜多隊が激突、いよいよ戦いは開始された。
画像は『関ヶ原合戦図屏風』における、「篠の才蔵」の異名を持つ可児才蔵の姿である。
背に篠を指し、槍ではなく長刀を携えているようである。
可児才蔵は斉藤龍興・柴田勝家・明智光秀・織田信孝・豊臣秀次・前田利家に転々と仕えた経歴を持つ、言ってみれば「渡り者」である。
しかし正則は彼の剛胆さと武勇に惚れ、七百五十石で召し抱えたと伝えられている。
東西両軍が激突
さて直政らはそこで向きを急に変え、島津勢へと掛かっていった。
地図上で彼らの道筋を辿ると判るが、非常に遠回りかつ不可解な動きをしているのである。
しかしこれには理由があった。
『関原合戦進退秘訣』に「本多忠勝、井伊直政ハ先手ノ目代トシテ内府ノ旗本ヲ遠ク離レテ相進マル且ハ島津兵庫頭義弘ハ西国第一ノ強将ナリ當之可破之トノ命ヲ蒙レリ」とある。
つまり、直政らは開戦のきっかけを作った上で島津勢を打ち破れとの命令を受けていたのである。
ただこれには異説もあり、そのまま宇喜多勢と戦ったとするものもある。
新井白石の『藩翰譜』では忠吉傳の按に「初メ井伊ガ守殿ノ御供セシ時ハ即チ我手ノ者共浮田ガ勢ト戦フ軍中ニ駆入テ軍ノヤウヲモ御目ニ掛シナルベシイカデ今日ノ大将軍ノシカモ纔ノ御勢ナルヲヨシナク多勢ノ中ニ御供シ(略)」とあり、彼らが宇喜多勢と戦った旨が記されている。
ただ、先述の島津勢に攻めかかったという説は『関ヶ原軍記大全』『當代記』『慶元記』など多数にわたる上に『関ヶ原町史』もこの説を支持しており、『関原合戦図志』の著者神谷道一氏も『藩翰譜』の説は新井白石の推論であろうとしている。
ここでは上記理由により島津隊に攻めかかったものとさせていただく。
では、なぜ井伊・松平隊が直接島津勢に向かわずにわざわざ福島勢の横を通って宇喜多勢に発砲したかであるが、これは推論だが福島勢を宇喜多勢と戦わせて釘付けにする目的があったと思われる。
戦闘力の極めて高い福島勢が一斉に向きを変え(位置的にはかなり無理があるが)、島津勢に攻め掛かられて戦功を挙げられては、家康から島津隊を討てとの命令を受けている直政らにとって、都合が悪かったのかもしれない。
さらに西軍の敗勢が決定して島津勢が敵中突破した際にも彼らは執拗に島津勢を追いかけているが、直政・忠吉ともに負傷して結局は追撃を断念している。
これも上記にある家康の命令があったからこそ、「死兵」の島津勢をもとことん追撃したと解釈することは出来ないだろうか。
彼らの真意は知るべくもないが、ともあれこうして戦いは始まった。
闘将島左近被弾
~午前九時の関ヶ原~
--------------------------------------------------------------------------------
福島勢が宇喜多勢に攻め掛けたのを機に三成や黒田長政も狼煙を上げ、両軍が激突します。
西軍は健闘しますが、三成にとって大きな誤算が生じました。
最も戦闘力が高く頼りにしていた島左近が、黒田隊の銃撃により被弾負傷してしまったのです。
--------------------------------------------------------------------------------
家康、前線へ移動
戦いが始まり、南宮山勢(毛利・長宗我部ら)の動く気配がないことを確認した家康は、遊軍の金森・遠藤・生駒・小出らを関ヶ原駅の北まで、山内・有馬・蜂須賀らを関ヶ原柴井にそれぞれ進めさせ、自ら関ヶ原駅付近へ移動した。
これは桃配山からでは関ヶ原一帯を鳥瞰することが出来なかったためである。
しかしこれは南宮山方面の敵情を正確に探知しないと危険であり、ある意味では家康の「賭け」だったかもしれない。
西軍に目を転じると、切り込んできた福島正則勢の先鋒福島丹波・同伯耆・長尾隼人隊と激突した宇喜多勢は、先鋒明石全登が八千(異説あり)の兵をもってこれを迎え撃つ。
部分的な戦いではあるが宇喜多勢の方が兵数に勝り、加えて明石以下長船吉兵衛・本多政重・延原土佐・浮田太郎左衛門らが健闘、正則勢を約500m程も押し戻す。
これが事実なら、突入した正則隊はほとんど自陣近くまで押し戻されたことになり、宇喜多勢の健闘が光る。
福島勢の星野又八は敵兵三人を討つが遂に戦死し、福島勢の死傷は大きかった。
これを見た正則は怒り、「目ヲイカラシ歯ガミヲナシ叱咤シテ」兵を励ましたと記録にある。
しかし東軍勢も黙ってはいない。
福島勢の劣勢を見た加藤嘉明・筒伊定次の両隊が加勢に駆けつけて側面から宇喜多勢を攻撃、まさに東西両軍の旗が入り乱れての大激戦となった。
島左近被弾
さて笹尾山はどうかというと、島左近・蒲生備中が柵に鉄炮を掛けて東軍勢に発砲するが、大きな戦いには至っていなかった。
しかし南の宇喜多勢周辺で大激戦となり戦機が熟したと見た三成は、一斉に柵を開かせて東軍勢へ突撃を命じた。
これにより島・蒲生隊は柵の外へ進み黒田長政・田中吉政・生駒一正・金森長近・竹中重門らに攻め掛かる。
注目していただきたいのは、この戦いで西軍から攻撃を仕掛けたのは、唯一三成勢だけだったと言うことである。
島左近と蒲生備中の戦闘力を全面的に信頼していたことの証拠であろう。
しかしここで思わぬ誤算が生じた。
黒田長政は朝鮮役以来個人的にも「恨み骨髄に達している」三成を討ち果たそうと画策、鉄炮頭菅六之介正利・白石庄兵衛に命じて鉄炮五十挺を預け、丸山山中を迂回して島隊の側面(北側)から銃撃させた。
油断していたのか敵中に深く入り過ぎたのか、島隊はもろに銃撃を浴び、左近まで被弾負傷してしまったのである。
左の画像は『関ヶ原合戦図屏風』に見える菅隊の様子で、中央馬上が菅六之介正利、左上白馬に跨っているのが白石庄兵衛である。
左近は兵に両脇を抱えられて後方に退き、これを見た長政は突撃を命じた。
しかし、総崩れにならなかったのは、蒲生備中が踏ん張っていたのであろう。
以下にその模様を記録から抜粋する。
「此時島左近ガ先手モロク崩レタルハ黒田甲州ノ銃頭菅六之助ガ打タル鉄炮ニテ島左近深手ヲ負ヒタル故ナリ」(『関ヶ原軍記大全』)
「生駒讃岐守、田中兵部大輔、竹中丹後守一番ニ相掛ルト雖モ石田ガ先手島左近浅堀ヲ掘リ柵ヲ振リケル故カヽリ兼子鉄炮ニ打チ立テラレ猶予スル所ヲ左近突テ出テ数町切靡ヶ及難儀候時黒田横合ニ石田ガ先手ヲ突退」(『関原合戦進退秘訣』)
天満山北峯の西軍小西勢へは、東軍の寺沢・一柳・戸川・浮田(直盛)の四隊が攻めかかった。
『関ヶ原合戦誌』によると、行長の先手はこれら四隊に忽ち撃破され、行長本隊の兵もこれに誘われて一戦に及ばず敗走したとある。
また『関原合戦進退秘訣』にも「小西摂津守行長ハ既ニ寺沢、一柳、戸川、浮田等ニ切崩サレテ逃走レリ行長ガ勢ハ先手ノミ暫ク相戦フト雖モ行長ガ馬廻備ハ一戦ニ及バズシテ敗ス」とあり、行長勢の早々の戦線離脱は三成にとって誤算だったであろう。
島津勢の奮闘
小池村の島津勢へは井伊直政・松平忠吉と共に細川忠興・稲葉貞通・加藤貞泰らが攻め掛かったが、島津義弘は泰然自若として動じなかった。
義弘は十文字紋の陣羽織に二尺二寸の太刀を帯し、白采を手に床几に腰掛け、端から見るとまるで座禅を組んでいるようだったという。
戦慣れした義弘には、この日の西軍が一つにまとまっていないことは痛い程良く解っていたのである。
もはや勝敗は決した。
この上は島津の名に恥じないような進退をするのみであると決めていたのかもしれない。
一説にこの時阿多盛淳が先鋒の豊久の陣へ行き「今生の別れ」を告げたところ、豊久は「味方の陣は弱気だから今日の槍は突けまい」と応えたという。
そんなところへ三成本陣から使者が駆け込んできた。
使者の名は八十島助右衛門という。
彼は三成の命を受けて島津勢に兵を進めるよう伝えに来た。
しかし馬上から命を伝えたため、「無礼な」と激怒した島津兵が助右衛門を馬から引きずり降ろす一幕もあったという。
三成は再三に渡って懇願するが義弘は応諾せず、ついに三成自身が島津陣へ赴くが、「今日の勝敗はもはや与り知らぬ事。
島津には島津の進退があり申す」と突っぱねられてしまう。
そして間もなく、東軍は多勢を武器に島津勢を包囲、一斉に力攻めで寄せて来た。
豊久と共に先鋒を受け持ったのは山田有栄である。
彼は鉄砲隊を率いて敵中に進むや整然と折り敷かせ、敵を引き寄せたと見るや一斉に発砲する。
煙の下から薩摩の勇士指宿清左衛門忠政が果敢に東軍勢の中へ斬って出、ここへ有栄が突撃を命じた。
さすがに小勢と言えども薩摩兵は強い。
島津勢は奮闘し、指宿忠政は東軍中を三、四町(約400m)も斬り回ったという。
しかしやはり兵数が違った。
東軍は一旦押し返されたものの多勢に物を言わせて入れ替わり立ち替わり島津勢を攻撃、まさに一進一退、勝敗はつかなかった。
画像は『関ヶ原合戦図屏風』に見られる、銃隊を指揮する阿多盛淳の姿である。
この頃、南では藤堂・京極勢が軍を進めて大谷・木下勢に発砲を開始、ここに関ヶ原における東西両軍の対峙ラインほぼ全てで戦闘状態に入った。
南宮山勢動かず
一方、南宮山ではどうだったか。
この時南宮山東麓に布陣していた安国寺恵瓊は、自ら南宮山に赴いて毛利秀元に対し、山から降り狼煙を待って参戦するよう求めた。
しかし秀元は「自分は年少なので軍事は吉川広家に任せてある」と断ったため、恵瓊は切々と豊臣家から蒙った恩を説いて翻意を促す。
そしてついに秀元は参戦を約束し山下に陣取る広家に出撃の命を伝えるが、広家は頑として動かなかった。
広く知られているように広家は家康に通じており、殊に安国寺恵瓊とはウマが合わず、恵瓊を憎んでいた。
結果論ではあるが、南宮山は家康の背後に位置している。
もしこの時点で毛利勢が参戦していれば、家康本陣との間に池田・浅野勢が控えているとは言え、東軍方の動揺は大きかっただろうと思われる。
結局、南宮山の毛利勢始め長宗我部等は終日動かなかった。
これは西軍いや三成にとっては、やがて起こる小早川秀秋の寝返りに勝るとも劣らない大誤算であった。
宰相殿の空弁当
~午前十時の関ヶ原~
--------------------------------------------------------------------------------
全軍が戦闘状態に入り、三成は自ら一隊を指揮して東軍勢に攻撃を掛け、狼煙を上げて南宮山と松尾山の部隊に参戦を促します。
左近が負傷したとは言え蒲生備中・舞兵庫らの奮闘で東軍勢を押し返しますが、南宮山と松尾山の部隊は動きませんでした。
--------------------------------------------------------------------------------
三成勢の奮戦
戦いがたけなわとなった頃、三成は笹尾山を降りて前線の島・蒲生陣へと現れた。
ここで戦況を分析した三成は高野越中・大山伯耆に二千の軍勢を預け、東軍勢の側面を攻撃させようと試みる。
しかし家康もじっとしているはずはなく、この様子を遙かに望見した家康は本多忠勝のもとへ使者を派遣し、寄合衆の織田有楽・古田重勝・船越景直・佐久間安政に命じて直ちに高野・大山隊を攻撃させた。
彼らは一斉に進軍して高野・大山隊を押し戻し、勢いに乗って三成の設けた二重柵の前へと殺到していった。
負傷した島左近や蒲生備中はこの状況を見て、もはや大砲によって攻撃するしか方法はないと進言、三成もこれを受け入れて本営から大砲五門を柵内まで運ばせた。
そしてこれを東軍勢に発砲、敵がひるんでいる隙に蒲生備中・舞兵庫・北川十左衛門らが兵を率いて突撃を敢行した。
そして三成は、頃は今ぞと狼煙を上げさせ、南宮山と松尾山の両部隊の参戦を促したのである。
同時に三成自身も麾下の兵を率いて討って出、この猛烈な勢いに東軍勢は約300mほども敗走したという。
記録にこうある。
「田中兵部少輔吉政其子民部少輔長顕モ白旗ヲ揮テ士卒ヲイサメ敵軍ヘ突入ケルガ敵猛勢ニシテモミ立ラレ三町バカリ頽ルヽ」(『武徳安民記』)
「関原之戦為賊将島左近、蒲生備中所敗。
兵皆病罷。
一正振臂大呼曰。
是決勝之機。
死而後巳。
何以病廃耶。
於是創者皆起。
病者復立。
殊死戦」(『垂統大記』)
三成勢はこうして奮闘し、あわや家康麾下勢へ突入かというまでの勢いを見せる。
歴史に「if」は禁物だが、この時松尾山の小早川勢はさておき、南宮山の毛利勢が動いていれば、結果はともかく戦況は一変していたであろう。
そういう事態になれば松尾山の小早川は寝返ったかどうかは微妙であり、老獪な家康のこと、一敗地にまみれることはないにせよ、かなり苦戦を強いられたに違いない。
関ヶ原にて三成が敗れたのは戦術が下手だったからではない。
その威望あるいは人格に拠るものかはさておき、人心を掌握できず西軍を一つにまとめられなかったことが全てであろう。
つまり、戦略面で家康に遠く及ばなかったのである。
一言で「格の違い」と言ってしまえば三成には酷かもしれないが。
三成勢は奮闘したが、東軍の寺沢・一柳・戸川・浮田らは小西勢を撃破した後、続いて宇喜多勢へと矛先を転じる。
宇喜多勢は先鋒大将明石全登らの奮闘で福島勢と一進一退の攻防を続けてい